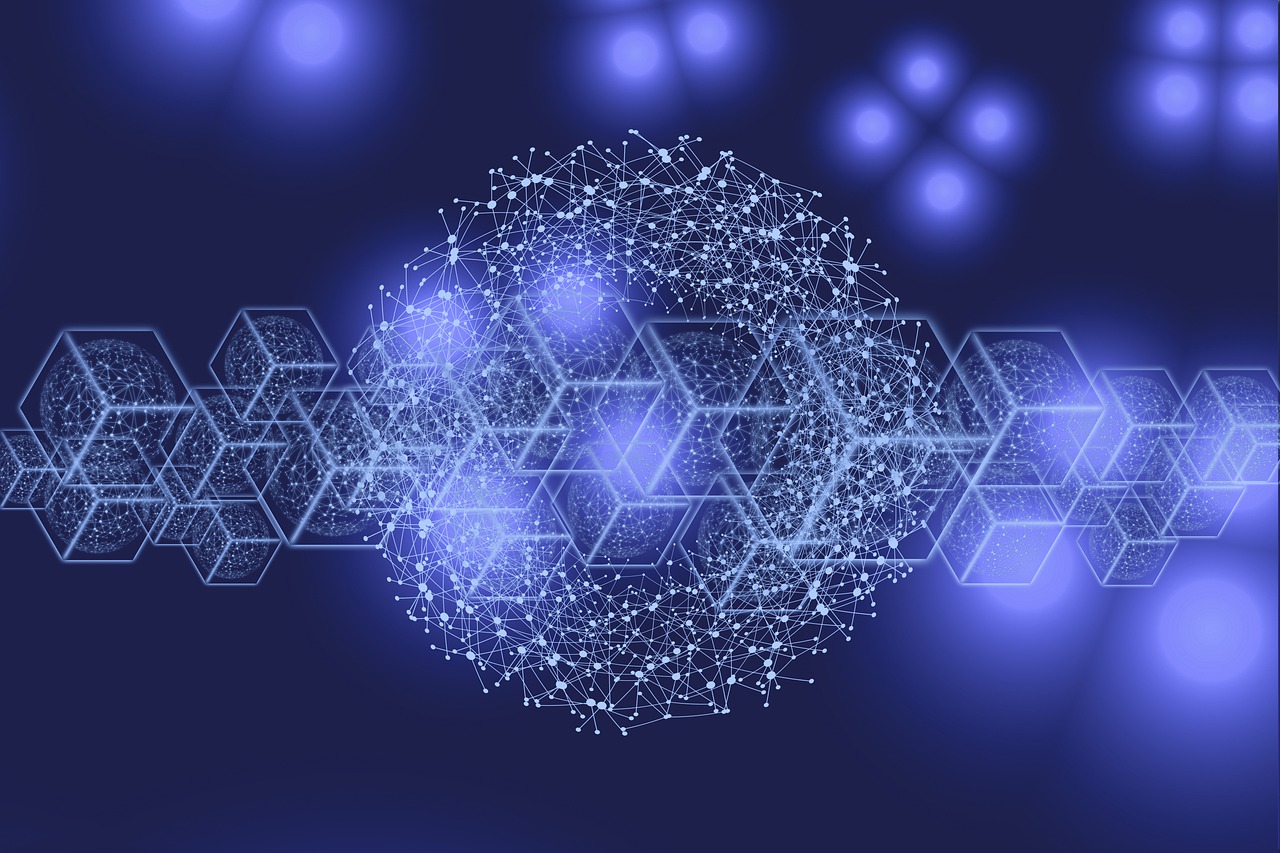ロシアとウクライナとの戦争は3年目を迎えている。イスラエルと、パレスチナ自治区ガザを実効支配するイスラム武装組織ハマスとの紛争も、2024年5月現在、収束の道筋が見えてこない。戦争は始める時よりも終える時が難しい。現在進行中の二つの戦争を見ていると、軍事的衝突に至らせないことの重要性を世界は改めて痛感させられた。
東アジアでは、中国が複数の国と領土問題を抱え、衝突を繰り返している。中でも、今後軍事的衝突に結びつきかねない、二つの国家間対立に注目する必要がある。一つが南シナ海における中国とフィリピンの海洋権益を巡る対立であり、もう一つが、中国とインドの国境を巡る対立である。
このうち、中国とフィリピンの対立はエスカレーションのリスクをはらむ。当初は中国海警船舶と、フィリピン当局の巡視船やチャーター船との警告合戦だったものが、最近では中国海警の放水により、フィリピン軍人3人が負傷するに至っている。一方、中国とインドの場合は、かつて死傷者を出すほど過激化したが、緊張が高まるたびに双方の自制が働き、エスカレーションが防がれている。
エスカレーションを招かず、事前に紛争を管理する能力は、日本にとっても不可欠だ。中国が尖閣諸島の領有権を主張し、海警を日常的に尖閣諸島周辺に展開しているからだ。そこで本稿では、中国と紛争を抱えるインドとフィリピンの状況を確認しながら、軍事衝突に至らせないためにどのようなメカニズムが求められるのかを探り、日本の安全保障上の示唆としたい。
自制し合う中国とインド
まず、中印の国境紛争について見ていきたい。中印国境は東西約3500㎞とされており、これは中国の東西距離約5000㎞の7割を占める。係争地域は、西からカシミール地域、ネパール西部、そして東部の「アルナーチャル・プラデーシュ州(インド呼称)」である。
国境地域はヒマラヤ山脈が連なり、高地のため軍を展開することが難しく、インド独立当初は同山脈が両国の緩衝地帯として存在していた。ただ、1950年代に中国がチベットを自治区として取り込んだことで、両国がヒマラヤ山脈を挟んで直接国境を接するようになり、緊張が高まった。62年に前述の係争地域各地において両国の軍事衝突(中印国境紛争)が生起、インド軍の敗走で終結した。
係争地域のうち、カシミール地域については、中印に加えパキスタンがプレイヤーとして加わる。数次のインド・パキスタン紛争に加え、パキスタンが中国に委譲した「カラコルム回廊」や中国が実効支配する「アクサイチン」を巡る紛争が、標高5000mの地域で繰り広げられている。
2020年6月には、アクサイチンにおいて中印両軍が衝突、インド側は軍人20名が死亡したとされるが、中国側の死傷者数は明らかにされていない。この衝突の特異性は、小銃や迫撃砲といった装備が一切使用されず、鉄の棒や石を武器に用いた点である。どちらかが銃を使用すれば、本格的な軍事衝突に発展する可能性があったが、双方が強く自制したとみられる。
同様の自制はインドが実効支配する東部アルナーチャル・プラデーシュ州においても見て取れる。今年3月9日、同州に建設中であった全長約3㎞の「セラ・トンネル」の開通式にインドのモディ首相が出席した。同トンネルを利用すれば、冬季でも兵力を国境まで展開できる。
こうしたインドの動きに対し、中国は「中国領土内での建設工事だ」と強く批判した。中国国防部報道官は3月15日の記者会見で、インドが国境付近で約1万名の兵力増強を行っていると非難、いわゆるアルナーチャル・プラデーシュ州はチベット自治区の一部であり、「中国固有の領土(territory inherent)」だと述べた。一方で同報道官は「インドと外交当局、軍当局のチャンネルは維持されており、中印国境は安定している」とも語った。
中国のインドに対する姿勢が自制的である背景には3つの要素がある。
第一に、国際的プレイヤーとしてのインドの立ち位置である。インドはグロ-バルサウスの中心的存在であり、中国とロシアが主導する地域協力組織SCO(上海協力機構)の重要な構成国でもある。2022年のジェトロ統計によれば、中印間の貿易総額は1180億ドルであり、米印の1314億ドルに迫る規模となっている。また、日米豪印の戦略枠組み「QUAD」による西側とのつながりも無視できない。中国を超える人口を持ち、IMF(国際通貨基金)の推計では、2025年にも日本を抜いて世界GDPランキングで4位に浮上するというインドの国際的存在感は中国としても尊重せざるを得ない。
第二に、軍事力である。軍事力を各種指標で評価する米国の軍事分析機関「グローバル・ファイアー・パワー」の2024年ランキングで、インドは中国に次ぐ4番手に位置する。さらには、核を保有し、その運搬手段である弾道ミサイルも保有している。ICBM(大陸間弾道ミサイル)の「アグニⅤ」は射程約5000㎞以上とされており、中国全土を射程に収め、中国に対する核抑止力として機能する。
最後に、中印間に政治、外交そして軍事と、幾層もの紛争回避メカニズムが構築されていることが挙げられる。アルナーチャル・プラデーシュ州のセラ・トンネルに係る摩擦が生起した直後の3月27日にも、中印国境に係る外交レベル協議である「第29回実務レベル協議(Working Mechanism for Consultation and Coordination:WMCC)」が開催されている。2020年の直接衝突の際も、現場指揮官レベルで兵力の引き離しに合意している。これら各レベルにおける交渉が継続的に行われていることが紛争をエスカレーションさせない大きな要因となっている。
南シナ海において、米国頼みのフィリピン
翻って、中国とフィリピンの南シナ海アユンギン礁を巡る対立はどうだろうか。結論から言うと、フィリピン単独では、中印で挙げた「エスカレーションを防ぐ3要素」を構築できず、米比相互防衛条約の存在が頼りと言える。フィリピン単体で見る限り、経済、軍事面ともにインドほどの存在感を持つとは言い難い。そして、何よりも、中印間で見られたような幾層もの紛争回避メカニズムが見当たらない。
3月27日の米比国防相会談終了後、米国防総省はアユンギン礁での中国海警局船舶および海上民兵による危険な妨害行為を非難した上で、「米国のフィリピン協力関係を再確認した」と発表。加えて、米比相互防衛条約は南シナ海を含む太平洋における、両国の海軍艦艇、巡視船、公船に及ぶと明らかにしている。中比の南シナ海におけるエスカレーションが防がれているのは、この米国のコミットメントに負うところが大きい。
幾層から成る意思疎通メカニズムの構築を
冒頭で述べたとおり、尖閣を巡り中国と対立する日本にとっても事前に紛争を管理する能力は不可欠だ。
2カ国の例を考察したが、米国頼みのフィリピンよりも高い軍事力、経済力を備え、中国と対話のチャンネルを持つインドのあり方は参考になる。グローバルサウスの中心的存在であるインドほどの勢いがあるとは言えないが、フィリピンを大きくしのぐ経済力が日本にはある。また、インドのように核保有による抑止力はないものの、日本の軍事力は相応に高く(米軍事評価機関「グローバル・ファイヤーパワー」によると、2024年の日本の軍事力は世界7位)、米国との同盟関係を有する。このように、日本の国際的地位と日米安保を基軸とする防衛能力は、紛争を管理する有力な手段だと言える。
一方、偶発的な衝突を含む紛争を回避するメカニズムについては、十分とは言えない。日中間で合意された海空連絡協議に基づく外交レベルのチャンネルについては、定期的な会合が開かれているが、設置するとされた中国人民解放軍と自衛隊のホットラインの実効性は明らかにされていない。さらに、現場レベルでの話し合いの場は設定されていない。
総じて、尖閣諸島を巡って、不測の事態が生起した場合の危機回避メカニズムは今のところ十分とは言えない。日米安保の実効性を確保することは言うまでもないが、それに加え、中印の関係性を参考に、尖閣周辺を行動する海上保安庁と中国海警局、さらには自衛隊と中国人民解放軍とが直接意思疎通や危機回避できるメカニズムの構築は、喫緊の課題と言える。いったん起こってしまうと終結が難しい軍事紛争を、政治、外交、軍事と幾層から成る意思疎通システムを作ることで、決定的衝突を回避し、紛争を管理する必要がある。
写真:代表撮影/ロイター/アフロ
地経学の視点
尖閣諸島周辺に、中国海警局の船舶が日常的に現れるようになって久しい。日々のニュースに取り上げられるだけに、「またか」という気持ちにさえなる。しかし、この「またか」という感情こそが、われわれの緊張感をそいでいるのかもしれない。
2010年に中国漁船が海上保安庁の巡視船に衝突する事件が発生した。漁船の乗組員は逮捕・送検され、日中間の外交問題にまで発展。漁船と海警船舶の違いはあれど、わが国もすでに、今日、南シナ海で起こっている中国による似たような暴挙を、身をもって経験しているのである。そのことを、忘れてはいないだろうか。
著者は以前の記事で、シーレーンの重要性を強調していた。尖閣諸島周辺で仮に大きな衝突が起これば、海上交通確保にも影響が出てくる。小さな火種が燃え広がらないよう、多重に対話できるメカニズムの構築は待ったなしと言える。(編集部)