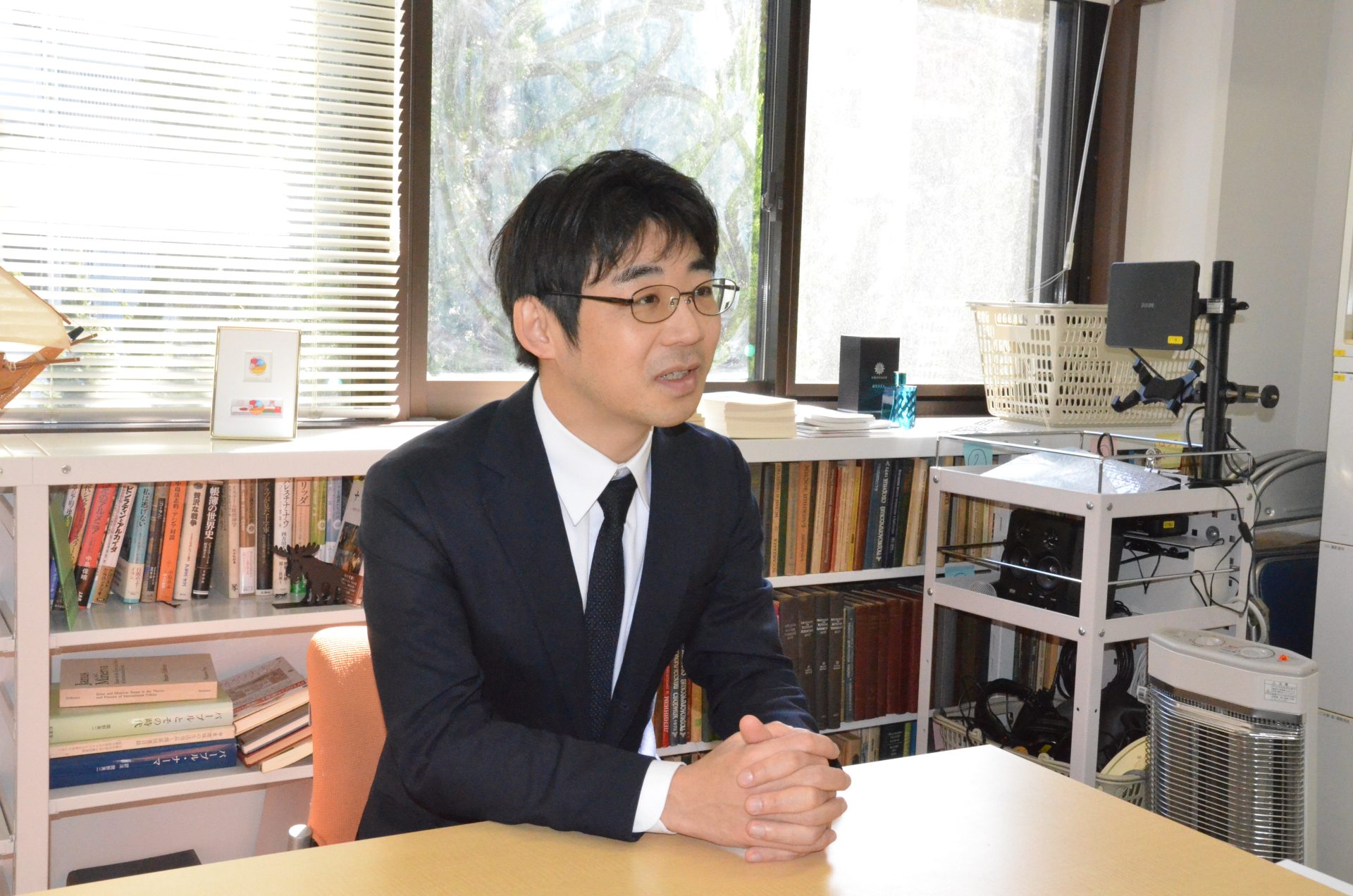いまや、人類の文明文化に欠かすことができず、かつその進展のカギをおよそ握ると言っていい微細な部品――「半導体」にまつわる国家と企業の攻防の物語を活写した『半導体戦争 世界最重要テクノロジーをめぐる国家間の攻防』は世界的なベストセラーになった。
同著が描いた、石油を超えるほどに極端に偏在した半導体製造プロセスをめぐる各国の思惑と駆け引きは、刊行後も留まるどころかむしろ加速している。地位を追われたかつての王者として描かれた日本は今、米中対立という地殻変動の間にできたわずかな隘路に向けて復活に挑む「最後のチャレンジ」に挑んでいる。
同著の著者クリス・ミラー氏(タフツ大学准教授)と、長年半導体業界をウォッチし、今は日本の半導体戦略策定にも関わる若林秀樹氏(東京理科大学教授)に、『半導体戦争』とその先について語り合ってもらった。
(構成:池田信太朗=実業之日本フォーラム編集長)
この記事の主な内容:
米国よりも日本が先に半導体の戦略性に気づいた
政府はどこまで産業に関与すべきか
日本凋落、台韓躍進の歴史をどう読むか
研究と開発のあわい、LSTCは成功できるか
次の焦点は「後工程」、チップレットの可能性
中国が台湾海峡を封鎖するというシナリオ
若林 日本の半導体戦略が大きく動き始めています。国家安全保障の観点からTSMCを誘致すべきという話は2019年頃から出ていましたが、日本の半導体の歴史を大きく転回させたきっかけは2つありました。2020年に西川和見さんが経済産業省の情報産業課長になり、半導体戦略の陣頭指揮を執り始めたこと。そして2019年に東京エレクトロンの社長・会長を歴任した東哲郎さんのところに米IBMから電話が入り、提携の打診があったことです。
2021年から私は経産省の「半導体・デジタル産業戦略検討会議」のメンバーとして議論に加わっていますが、最初から3回目までは、会議の雰囲気は冷めたものでした。そこでの多くの意見は「日本の復活は無理だ」「TSMCが日本に来ることは決してない」というものだったのです。しかしTSMCが九州に工場を新設するという方針を決めたあとくらいから会議の雰囲気が変わり、いまは熱気に満ちています。
ミラー まず根底に2つの大きなトレンドがあります。それらの潮流があってこそ、日本の産業界も政府も、半導体に力を入れなければならないと考えるようになったのだと思います。

1つ目は、半導体技術の重要性があらゆる分野で増しているということです。分かりやすい例ではスマートフォンがありますが、それには留まりません。例えば、数多くの半導体を搭載している自動車は一例です。あらゆる産業で半導体の重要性がますます増しています。これに伴って、年々、半導体の需要が世界的に拡大し続け、膨大な規模になっています。先端的な半導体のみならず、いわゆるレガシー半導体も含めて需要が大きく伸びています。
2つ目に、その半導体のサプライチェーンの極端な偏りがあります。この10年を見てみると、とりわけ先端半導体の製造が、台湾のある1つの企業(注:TSMC)に大きく依存するようになりました。しかも、それと時を同じくして、その企業が位置する台湾に対する中国の軍事的な脅威が高まってきました。
つまり、あらゆる産業の趨勢を決するほどに重要な存在になった半導体が、台頭する中国の脅威にさらされている台湾に位置するたった1つの企業に握られている。この状況が日本政府を突き動かしたのでしょう。
この数十年、半導体製造における日本のシェアは大きく下がってきました。日本政府はこれに対して、外資の誘致も含めて、国内における半導体産業への投資を増大させています。半導体製造国としての日本の重要性を復活させ、維持したいという意思を見せたということだと思います。とりわけ、先端半導体については日本で生産する、ということが、日本政府と日本の産業界の戦略の中心に据えられました。ラピダスの創設はその表れですね。
米国よりも日本が先に半導体の戦略性に気づいた
若林 いつも日本政府の支援は「遅すぎて、小さすぎる」、中途半端でリスクが取れない傾向があったと思います。しかし今回は、政府は素早くかつ大胆に支援を決めました。米国アリゾナでのTSMC工場の建設計画は遅々として進んでいないとも聞いていますが、日本では熊本でTSMC工場建設が進み、北海道ではラピダスの工場建設の計画も具体的に進んでいます。こうした日本の変化に対して、欧米の政策担当者と会った際には「一体、何があったんだ」と驚かれました。どうご覧になっていますか。
ミラー そもそも世界の主要な国々の中で、日本の動きは早かったと思います。日本政府の内部で、この半導体という分野が抱えるジレンマに着目し始めたのは5年から7年ぐらい前のことだと思います。
私は『半導体戦争』を書く前、NSCなどに所属する、米ドナルド・トランプ政権の何人かの高官たちと話をしました。そこで「なぜ、半導体に目をつけたのか」と聞いたところ、「日本から『これが重要になる』と聞いたからだ」という返事が返ってきました。これはおもしろいなと思いました。
日本がここ数年で取ってきたアプローチは、もちろんCHIPS法による規制などを進める米国や欧州と軌を一にしているというところはありますが、それだけではなく、かなり独自の、欧米とは異なるアプローチがあったと思います。例えば、若林さんが挙げたTSMCの工場の誘致、あるいはラピダスを創設するといったような具体的なプロジェクトが進められたという点はもっとも大きな違いです。
こうした動きは、日本はほかの国に比べてより大きな賭けをしているとも捉えられると思います。うまくいけば大変よい結果を生みますが、うまくいかなかったらリスクも大きい戦略と言えると思います。
若林 確かに日本は大きくリスクを取る方向に舵を切ったと思います。1980年に「新エネルギー総合開発機構」として設立されたNEDO(現・新エネルギー・産業技術総合開発機構)は、その名の通り、もともと石油代替の太陽光などの新エネルギー分野に特化した国立研究開発法人で、その後は様々な分野の「技術開発」を担ってきました。経済産業省はこのNEDOを半導体戦略の「社会実装」——生産設備導入や工場建設などのために活用すべく、「ポスト5G基金」や「グリーンイノベーション基金」などを創設し、総額1兆円を超える規模でTSMC熊本工場の建設やラピダスの立ち上げを支援しようとしています。
ミラー 半導体の世界においては、投じる金額の大きさは大きなインパクトを生みます。逆に言えば、先端的な半導体を作ろうとすれば、何億ドル、何十億ドルという巨額の資金が必要になるのです。ですから、大胆に多額の資金を投じる日本政府の決断は正しいと思っています。すでに半導体産業を抱えている国はその地位を守るために、これから育成しようとしている国はキャッチアップするために、どこも巨額の資金を投じて、直接的な補助金のほか、税制控除などの優遇策も駆使しながら競争しています。欧米はもちろん、韓国や台湾、インドなどがその競争に加わっていますし、中国は一国でそれらの国々が投じている金額の合計を上回るような資金を投じています。
若林 今が日本にとって絶好の、そして最後かもしれない好機だからということもあると思います。
およそ50年前、1970年代、田中角栄首相は「日本列島改造論」を打ち出し、新幹線や高速道路を日本列島に張り巡らせることによって日本を変革しようと試み、その後の成長の礎を築きました。1970年当時、円相場は1ドル360円に固定されていて、旺盛な輸出を謳歌していました。インフレーションもありました。そして日米関係は非常に良好でした。しかしその後、日本経済は円高・デフレに見舞われ、1980年から数十年、日米関係は以前ほど良好ではなくなり、長い停滞に苦しみます。そして今、円安・インフレが進行し、日米関係が大きく改善しています。この環境は、1970年代と似ています。実際のところ、現状は1ドル130円台後半〜150円ほどですが、日本の本当の実力から見ると200円以上でもおかしくありません。

私は昨年『デジタル列島進化論』という本を出し、そこでも触れたのですが、いま申し上げた数十年ぶりの好機をとらえてこれから日本がすべきことは、今度は交通網でなく、情報通信網やデジタルによる変革であり、それを支えるのが半導体だと思っています。
政府はどこまで産業に関与すべきか
若林 政府と産業政策の関係について議論したいと思います。米国は、「見えざる手」が統べる自由市場の力で40年から50年ほど成長を謳歌してきましたとされますが、実際は、政府が産業政策によって市場を制御してきたと思っています。しかし日本は自由放任でいいと勘違いし、また、日米摩擦を経て米国からの批判を恐れるようになって、無策とは言いませんが有効な産業政策が打ち出せず、結局のところ、多くの企業が小さな市場で競い合って体力が蝕まれていきました。これが日本の産業が衰退した理由だと思っています。
ミラー ある意味では、世界は全体として、また再び貿易紛争あるいは貿易競争の時代に戻りつつあるのかもしれません。ただ重要なのは、そこをあまり過大に評価してはならないということ。逆に言えば、地政学的な要素というのを過小評価してはならないということです。概して言えば、80年代あるいは90年代の日米摩擦と、今、中国が多くの国との間で抱えている緊張関係というのは、やはり違う側面が大きい。地政学的な、あるいは安全保障法上の摩擦という側面が大きいからです。
半導体の分野で分かりやすく言えば、80年代の日米の間の半導体をめぐる争いというのは、関税、補助金、あるいは産業政策をめぐる論争や競争でした。もちろん米国や日本、あるいはほかの国々も、中国に対して、今もそうしたことを議論しています。しかし、それ以上に、やはり軍事、あるいはインテリジェンス分野における半導体の利活用についての懸念が非常に大きくなっています。技術が、その懸念を呼ぶのに十分なほどに、あまりにも進歩してきているからです。半導体という技術を巡る摩擦の中心に、安全保障、軍事、あるいはインテリジェンスということが据えられているということはしっかり押さえておくべきでしょう。
一方で、若林さんのおっしゃったことに私も同感だと思う部分もあります。現に日米欧とも、やはり中国の(半導体分野などに対する過度の)助成金についてはもちろん問題にしています。現実として、世界は、以前のような市場メカニズムが支配する制度からどんどん離れようとしてきているということでしょう。各国政府が、もう不可避的により大きな役割を果たしつつある。そういう世界になってきているということです。
ですから、これから考えなければならない問題というのは、半導体市場における政府の果たすべき役割をどう定義するのか、ということだと思います。安全保障上の懸念に対処するということと同時に、経済の効率性も追求しなければならない。要は、政府が介入することによって、その問題解決にかかる必要以上のコストをかけてはならないということです。しかし、ここで正しいバランスをとるのはなかなか難しいと思います。日米欧の政府は、それぞれが独自にやるということだけではなく、全体として、どう半導体産業というものと向き合っていくのかという視点が欠かせないと思っています。
若林 政府の補助は過大になる傾向がある、つまり効率が悪くなる傾向があるけれど、しかし、やらざるを得ない。バランスを模索していくしかないというお話でしたが、これまでの産業史を振り返って、政府による補助が奏功したケースはあるのでしょうか。あるとして、どんな共通点があるのでしょうか。
ミラー すでに、ある国で先端的な産業が確立されていて、別の国の政府がそれに追いつこうとして産業政策を進めたような場合には、多くの成功事例があります。例えば韓国政府は半導体産業を育成しようとして支援を大々的に進め、成功しました。米国や日本が、すでに先端的な半導体産業のあり方を確立していて、これに追いつこうとした事例です。
一方、産業政策を有効に機能させるのが難しいのは、すでにその国が、より先端的な技術を確立している、先端に立ってしまっているという場合です。既に決まっている目標に追いつこうとするよりも、新しく目標を作り出すということは、より難しいということだと思います。
ただ、こと半導体産業の歴史を振り返ってみると、多くの国々で、他国に追いつくプロセスだけでなく先端的なプロセスにおいても、常に政府の介在がありました。特に長期の研究開発の資金をつける、そしてプロトタイプをつくるというプロセスは、政府が担うことが多かったと思います。例えば米国では、新しい技術が生まれたら、政府、とりわけ国防総省がこれを試すという役割を引き受けてきました。しかし、その先の、商業ベースにのせて産業にしていくという任務については、政府が役割を果たすことが難しくなります。マーケットのシグナルを常に受け取り、対話しながら、慎重に微調整しつつ進めていく——。政府が長けている要素技術の開発やプロトタイプ化とは、まったく異なる課題設定や解決が求められるからです。
政府が半導体分野に多額の資金を投入するという場合、キャッチアップ、先端開発と駒を進められたとしても、さらに、果たしてそれが商業的に実現可能かどうかというリスクを常に伴うということです。これが半導体分野における産業政策の難しさです。
若林 中国はとりわけ多額の補助金を半導体業界に注ぎ込んできましたきましたが、その成否をどうご覧になっていますか。
ミラー おっしゃる通り中国政府は、ほかのどの国と比べても遥かに大きな規模の助成金を自国の半導体産業につぎ込んできました。中国政府が半導体を、習近平国家主席の呼ぶところの「中核技術」として指定したのが2014年のことです。10年弱の間、大規模な基金が設けられ、国から地方政府から、半導体業界に多額の支援がなされてきました。
しかし実際には、その資金は正当に管理され、有効に活用されてきたとは言い難いと思います。配分をめぐって汚職がはびこったということもあります。例えば、ある最大規模の1つである半導体助成金は、不動産投資業界の出身者が管理のトップを担っていました。半導体業界のことを何も知らないこうした人物が、半導体開発投資を担う基金の運営に携わるベストな人材とはとても言えないと私は思います。

こうした状況をつぶさに見ていく中で、中国政府は、半導体という分野で果たして正しい産業政策がとれたのかどうかという問いを立てるとすれば、私の答えは「ノー」ということになります。
中国は、有効な産業政策をどう進めるべきかという点について、研究すべきよい事例を提供してくれています。2社ほど成功事例がありますが、数多くの失敗事例も見られます。政策多額の資金を投入すれば、確かに一部は成功する。他方、お金をばらまくだけでは効果は上がらないこともある、ということです。中国政府を世界的なベンチャーキャピタル企業を比較してみれば、そのパフォーマンスは大きく劣後していると言わざるをえません。
日本凋落、台韓躍進の歴史をどう読むか
若林 日本は、1980年代まで、半導体分野などで米国が恐れるような一流の技術力を持ちながら、しかし軍事的な野心は持たないという地位を受け入れてきました。だから米国は日本をよきパートナーと見てきたのだと思います。しかし、クリスさんが『半導体戦争』でも触れておられましたが、日本をナンバーワンとしたい、「ノー」と言える日本でありたいというソニーの盛田昭夫や石原慎太郎の主張が、「経済や技術でトップになった国は、軍事でもトップになりたいという野心を持つ」という懸念を米国に抱かせたのだと思います。これが、日本にとっては失敗であり、その可能性を米国は許さなかったということだと思っています。日本は米国のお蔭で自由主義経済を最も謳歌したのに、とんでもないと。
しかし、ここでお聞きしたいのですが、なぜ韓国と台湾の半導体産業は成功できたのでしょうか。韓国は、かつての日本と同様、メモリー分野で首位を走っています。台湾はTSMCなどのファウンダリで世界に欠かせない地位を築きました。米国には、韓国や台湾が軍事的野心をも持つという懸念はないのでしょうか。
ミラー 1980年代の日本の半導体産業をどう見るべきかと考える時、2つの視点いずれに立つかで見えてくる光景が全く異なると思っています。
1つはDRAMのメーカーの視点です。日本のDRAMメーカーは世界で大きなシェアを握っていましたが、あまりにも事業の拡張ばかりに目が向いており、過剰投資に走っていました。当時は銀行との関係も良好で、低利で融資を受けられ、しかも株主も収益性よりも市場シェアにフォーカスするという経営を許していました。米日間の貿易摩擦は、このDRAMをめぐっての摩擦でした。
しかし視点を移すと、DRAMメーカー以外のプレーヤー、例えば装置や素材を扱う企業は、摩擦に直面していたわけではありません。こうした企業は長期にわたって生き残り、今も成功しています。
誤解すべきでないのは、今も生き残る装置や素材などのメーカーは、摩擦から逃れたから生き残ったのではなく、非常に効果的なビジネスモデルを持っていたから勝ち残ったという点です。日本のDRAM勢は、過剰投資、過剰生産によって米国の企業を押しのけることに成功しましたが、その後、日本企業同士の激しい競争に陥り、お互いに市場と利益を食い合って自滅していく状況が生まれてしまいました。一方、装置や素材などの分野のプレーヤー、例えば東京エレクトロンやJSRは、摩擦を免れただけでなく、そこから何十年にもわたって効率的で強靭なビジネスモデルを築き、成功を続けてきました。
つまり、総じて言えば、80年代の日米摩擦は、半導体産業のほとんどには影響を与えなかったということが言えると思っています。ただDRAM分野だけは非常に特異な状況に置かれ、摩擦が起きましたが、摩擦の有無に関わらず日本のDRAM企業はまずい経営をしてしまったということです。
では、なぜ韓国はDRAMで大きく台頭できたのでしょうか。韓国企業は、米国企業からライセンスを成功裏に取得することができていたということがあります。また、賃金などのコストが日本に比べると低く、競争力を作りやすかったということもあります。しかし、何より大きいのは、日本のDRAMメーカーが不毛なシェア争いを続けて損失を出し続け、ついには自ら撤退せざるを得なくなっていた、ちょうどそのタイミングで韓国企業が参入することができ、置き換わることができたということです。韓国企業は、日本企業と同じ轍を踏まずに設備投資もうまく進められました。
日本の半導体産業にとっての本当の意味での悲劇は、80年代にシェア争いに明け暮れて疲弊したDRAMメーカーが退場を余儀なくされ、韓国企業にその座を譲り、半導体市場がロジック半導体を主人公として大きく変わる1990年代という極めて重要な時期に、次代に向けた投資ができなかったということです。そして、繰り返しになりますが、それは貿易摩擦ゆえではなく、市場のシェア競争ばかりに目を向けていた80年代の日本のDRAMメーカーの経営のまずさに帰すべきことだと思っています。
若林 なるほど、私も当時は半導体分野を含め電機業界をウォッチするアナリストで、DRAM事業の経営の拙さについて警告を出すレポートを書きました。装置メーカーも分かっていたと思います。しかし、総合電機メーカーに傲慢や油断があったのは確かですね。
研究と開発のあわい、LSTCは成功できるか
若林 日本政府は、半導体強化策の中で、ラピダスだけでなくLSTCという半導体技術センターを設立しました。これは、極めて重要な役割を果たすと考えています。米国が設立したNSTC(国立半導体技術センター)のモデルに倣ったものです。ほかにも、米国ではかねてDARPA(国防高等研究計画局、軍用新技術の開発と研究を担う米国防総省の機関)が研究と事業の橋渡し役として機能しているし、SEMATECH(次世代半導体の製造技術の確立に向けたロードマップ策定を担った米国の官民合同コンソーシアム、1987年設立)のような取り組みもありました。欧州では、IMEC(大学際微細電子工学中央研究団、超微細電子工学と情報通信技術の分野で研究開発を担う、ベルギーに本拠地を置く非営利団体。2018年にオランダの半導体装置メーカーASMLと共同で次世代露光技術EUVの研究開発を進める研究所を開設した)もありますね。

翻って日本のLSTCはうまく機能するか、少し心配しています。研究所でなく開発センターとして機能すべき政府機関ですが、メンバーを見るとそのほとんどがアカデミア出身です。彼らはアカデミックな分野には興味を持っていますが、商業化や社会実装には弱いかもしれません。
ミラー 米国のNSTCは、まさに、今試みが始まったところで、成果を上げられるかどうかを判断するのは時期尚早だと思いますが、いずれにしても、これから焦点を当てるべき分野というのは、おっしゃる通り、新しい技術を、いわゆるラボ(研究室)からファブ(工場)へと、研究から製造へとどう結びつけていくのか、その道筋をどうつくるのかというところだと思います。基礎研究については、日米の大学で、物理学や材料化学などの分野ですばらしい研究がすでに進んでおり、成果も出ていると思いますが、果たしてそれらの研究成果が実装できるかどうか、商業化できるかどうか。
一方で企業側を見ていくと、まずそもそも半導体は、医薬やバイオなどと並んで、研究開発に最も大きなコストをかけている産業です。ただ、R&Dと言った場合、R(研究)よりもD(開発)の方に、より注目する傾向があります。うまくいきそうな技術を見出し、実際にどのように製品に変えていくのかというところに注力しているということです。半導体産業はかなり長期のリードタイムが持てる業界なので、多くの資金をかけてこの実用化を進めることができていると思います。しかし一方で、非常にラジカルな、抜本的にこれまでの地平を一変させるような技術にはなかなか手が付かないという欠点もあります。
つまり、研究領域では、基礎研究は非常に優れた成果を出していて、技術の境界線をどんどん先に伸ばしていこうとしている。そこはうまくいっている。企業も、有望な技術を微調整して、実用化する部分は長けていてこれもうまくいっている。しかし、その中間の部分、すなわち、新技術の種を見出し、道筋をつけて、実装の可能性を模索しながらテストしていくというプロセスが、今のところ欠けているのではないかというのが私の見方です。
若林さんが挙げておられたDARPAの役割がまさにそれでした。ものになるかどうかわからないアイデアを集め、プロトタイプをつくってみて、うまくいきそうか試してみる。多くはうまくいかないんですけれども、1つでもうまくいきそうなものがあれば、企業を説得して、それを量産化に持っていくということで成功してきました。IMECの挑戦もこの領域でしょう。研究室で新たな技術が生まれ、これが実装可能だということが実証され、TSMCやインテルがそれを取り上げてどんどん量産化に持っていく。そういう循環を作るために、研究機関と企業の価値を繋げられるかが問われることになると思います。
LSTCのメンバーがアカデミズム色が強すぎるというご懸念についてはよくわかります。こうしたプロジェクトでは、往々にして、学会から有力な研究者を連れてきて担わせるということをやりますが、そうした人材が期待する役割を果たせないことは確かにあります。学者的な考えしか持っていない人だと、基礎研究をいかにして産業につなげるか、両者のかけ橋としてどう結びつけていくのかということに長けていないと思います。実は、そういうことに向いているプロフェッショナルというのもいると思うのですが。
若林 おっしゃるように、技術の実用化には、研究と開発、さらにその先の事業化までの橋渡しが重要ですね。舛岡富士雄さんが発明したNAND型フラシュメモリはその好例だと思います。彼はもともと研究所に所属する研究者でしたが、工場に移り、製造における歩留まり改善などに貢献し、さらに工場の外にも出て顧客向けに営業もしました。これがバリューチェーン全体への技術移転をもたらしたと思います。もし彼が研究所だけに留まっていたら、生産技術面の改善も難しく、顧客ニーズを開発にフィードバックすることもできなかったと思います。
次の焦点は「後工程」、チップレットの可能性
若林 次いで、「後工程」を含めたサプライチェーンの話題に移りたいと思います。TSMCが熊本に来たということは素晴らしいことだと思いますが、これで「国産化」できるようになるのは半導体製造の「前工程」に該当する部分だけです。熊本のTSMC工場が加工したウェハーは、台湾に運び、後工程を担うOSAT(パッケージングを総合的に担う後工程請負会社)に依頼して、それをまた輸入しなければなりません。さらにサプライチェーンを見ると、その先には半導体を組み込んで製品を製造するEMS(電子機器受託製造サービス)もあります。実はファウンダリ以上にOSATもEMSも台湾に集積しています。
これでは、貿易赤字は減らず、サプライチェーンは依然として長いままです。OSATやEMSも国内にないと、日本の課題について本質的な解決は得られないと考える向きもあります。
ミラー 「後工程」をどうしていくかは重要なテーマになっていくと思っています。後工程には人手がかかるので、労働コストが有利な南アジア、台湾、中国などに集約されていきました。また、OSATは、日米欧にはほぼありません。
しかし、これを変えようとするのは非常に困難だと思っています。いま、やはり「多角化」をどう図るのかという議論が始まっていると思いますが、これは正しい方向に向いていると思います。日本は、OSATをオンショアリング(日本国内に誘致)できるかどうかという命題よりも、供給の多角化をどう図っていくのかという命題として、この問題を捉えるべきではないかと思います。
例えば、ここ最近の出来事では、マイクロンがパッケージングをインドでやるということを発表しました。インド政府も、いわゆるアセンブリ、パッケージングサービスなどの大国になろうという方針を打ち出しています。東南アジアを見ても、マレーシア、タイ、フィリピンなどの国はやはり可能性を持っていると思います。こうした国々とどう連携してサプライチェーンを多角化していくかという方向にいったほうが、実現可能なソリューションになるのではないかと思っています。
若林 オンショアリングすべきかオフショアリングでもいいのか。これはアプリケーションにもよると思っています。例えばスマートフォンやパソコンなどグローバルな巨大市場を形成している汎用性の高い半導体はインドに後工程を置いてもいいと思います。しかし、自動車やロボットなど日本にとって戦略性の高い分野、あるいは高度なセキュリティが求められる国内のデジタルインフラなどに使われる半導体は、短納期かつ地産地消で、国内でサプライチェーンが完結していることが望ましいと思っています。小池淳義社長がラピダスで挑もうとしている「短TAT(ターン・アラウンド・タイム=納期)」戦略の狙いはそこです。
コストについては、ゲームチェンジする可能性があるのではないかと注目しているのが、別々に製造された半導体チップを1つの基板上でブロックのように接続する「チップレット」がもたらすインパクトです。これにより、前工程の配線工程のデザインルールと後工程のパッケージのデザインルールが近づき、コスト構造が変わります。これまでは前工程は設備のコストが重く、後工程は人件費が重かったのですが、チップレットが実現していくと後工程も設備投資が重くなり、コストに占める人件費のウェイトが落ちていきます。また、そもそも日本の賃金は、円安の傾向が続けば韓国や台湾に対して競争力を持っていくかもしれません。
ミラー 確かに、企業が先端的なパッケージングにより依存するようになり、いわゆるパッケージ集約型に向かっていくのであれば、コストがどうなるかが成否を分けることになると思います。ただ一方で、パッケージングについても自動化が進んでいく可能性は高いと思います。また、若林さんがおっしゃるようにチップレットの方向に進んでいくということなれば、より差別化されたパッケージングが求められる時代が来るようにも思います。しかし、本当にコストを下げていけるのか、もともと低コストの国々に対しても優位を形成できるのかと言われれば分からないところがあります。
若林 昨今、TSMCは後工程にも関心を強めており、技術を強化しています。製造装置メーカーの米アプライド・マテリアルズ(AMAT)も、M&Aや提携を加速させて後工程分野を強化しています。前工程のプレーヤーが後工程に触手を伸ばしているという構図です。
迎え撃つ後工程のプレーヤーを見てみると、今は、製造装置も材料も、それらの技術も日本は強いと思います。しかし問題は、中小企業が多いことです。オーナー企業が多く、後継者問題を抱えている会社も少なくありません。このままではAMATやTSMCに駆逐されてしまう可能性があります。私は、今後、これらの製造装置や材料の中小企業を統合することが必要となるのではないかと考えています。経産省はこれまで、デバイス、装置、材料など大企業が多い前工程ではうまく舵取りを進めてきたと思いますが、後工程は違ったやり方が必要となると思っています。
ミラー パッケージングの業界が、今後、どう変わっていくのかというのは非常に興味深いです。製造のプロセスを見てみると、もう決まった企業の存在があって、ほとんど新規参入が見られません。しかし、パッケージングのセグメントは、どんどん新しい企業が進出してきて、しかも伸びています。新たな装置への需要も高まっています。非常にダイナミックに動いていて、エキサイティングだと思っています。
ただ同時に、そのような状況であるということは、既存のパッケージングの企業が、5年先、10年先に今のポジションを保つのは容易ではないということも意味するので、生き残りをかけて常にイノベーションを起こしていかなければなりません。よりよく変わっていかなければならないということだろうと思います。
若林 チップレット、光電融合などの新たな技術が半導体製造の分野で「モア・ザン・ムーア」(ムーアの法則を超える)の世界を目指しており、また量子コンピュータやニューロコンピュータなどの非ノイマンコンピュータの可能性も見えてきました。これらの新たな技術がもたらすインパクトについてどう見ていますか。
ミラー 答えとしては「誰にもまだ分からない」というところではないでしょうか。確かに、組み合わせとして異質(ヘテロジニアス)なもの同士の統合が進んでおり、アーキテクチャについても、産業を大きく変えるものが出てきています。
例えば、GPUはその最初の事例でしょう。もともとコンピュータグラフィックスでも大きな成功を見せていましたが、さらにAIの分野でも重要な役割を担うことが分ってきました。そこにNVIDIAのような1兆ドルの企業も生まれてきています。ただし、GPUの成功は「たまたま」と言っていいと思います。AIにもたまたま大きく役に立った、ということでしょう。
今後は、半導体の製造や設計においても「ルネッサンス」と言えるような新たな技術が、GPUのような大きな成功を狙って仕掛けられてくることになるでしょう。大きな機会を生むと思います。新しいアーキテクチャが出てくると、産業界全体が統合・再編をされ、異質なものが統合していき、新たな価値が生まれてきます。
ただ、どの企業、どの部門が勝つのかは、まだよくわかりません。パッケージング企業ではないか思いますが、パッケージングは、技術の進歩の上で、研究開発があまり得意でないプロセスなので苦しむことになるかもしれません。逆にファウンドリとか、装置メーカー、材料メーカーなどが大きく恩恵を受ける可能性もあります。どのようなかたちで「異質な統合」が進むのかということはまだ分からず、見守っていきたいと思っています。

若林 ChatGPTの登場で、一般にもAIの有用性や可能性が広く認識されました。先日、東京大学大学院工学系研究科附属システムデザイン研究センターの黒田忠広教授が、半導体のデザインをAIを用いて自動化するデモンストレーションを示して話題になりました。AIが半導体産業にもたらすインパクトについてどうご覧になっていますか。
ミラー 半導体業界は、製造プロセスからデータを収集し、高度なデータ分析技術を使って製造プロセスを改善し、ツールを改善し、サプライチェーン全体を改善するという試みにおいて最先端を走ってきたと思います。今後数十年、AIが様々な産業に応用されていくことは間違いないし、半導体も例外ではないと思います。ただ、コンピュータのこれまでの歴史を振り返ってみると、革命的な技術は、実は普及するのがかなりスローであるということも言えます。例えば5年先、さらに進化した最新のAIが果たして半導体産業に大きな飛躍をもたらしているだろうかと考えると、私はなかなか難しいのではないかと思っております。つまり、AIが半導体産業に与える影響については、短期的にはそこまで期待できないのではないでしょうか。たとえAIが現在の半導体需要を牽引しているとしてもです。
中国が台湾海峡を封鎖するというシナリオ
ミラー コロナ禍で物流が滞ったことで、長距離に及ぶサプライチェーンのリスクに気づいたという向きがあります。しかし私は逆の見方をしています。パンデミックが起きて、確かにしばらくはマスクなどの不足はありました。しかしこれは1世紀に一度起こるか起こらないかという規模のパンデミックだったからこそ起きた問題です。今から振り返って見るならば当然のことでした。パンデミックのごく初期を除けば、その後は、長距離に及ぶサプライチェーンを経由してモノは十分に提供されていました。例えば、私を含めみな自宅に引きこもっていましたが、それでもアマゾンで注文すれば、はるばる中国から玄関まで商品が届きました。コロナ禍は、逆にサプライチェーンの地理的な距離の長さはあまり問題ではないということを示してくれたと思っています。
半導体も例外ではありません。コロナ禍にあって、多くの国で様々な規制がなされ、予測できないような状況に置かれていたにも関わらず、半導体産業は逆に繁栄しました。2019年よりも2020年の方が生産は旺盛で、2021年、2022年とさらに増大を続けました。結果、ここ数年来の大きな繁栄を見ました。サプライチェーンの強靱性のよい証拠と言えると思います。
ではサプライチェーンのどこにどのようなリスクが潜んでいると評価すべきでしょうか。 私が見るに、2つの中国リスクだと思っています。
1つは、中国がサプライチェーンをいわば「武器化」すること。サプライチェーンを政治的な道具として使うということです。そしてもう1つが、中国が台湾を封鎖するという挙に出たらどうなるのかということです。
半導体産業だけではありません。例えば欧州におけるエネルギーのサプライチェーンがウクライナ戦争に受けた影響の大きさを見ればわかります。地政学というものが、いかにサプライチェーンに影響を及ぼすかということだと思います。
若林 日本にとっても、世界の半導体産業にとっても、重要な拠点が東アジアに集中しています。おっしゃる通り台湾はその最たるものであり後段にお聞きしますが、その前に、朝鮮半島にも大きな地政学リスクがあると思います。これはどうご覧になっていますか。
ミラー まず、韓国についてはそれほど心配していません。確かに北朝鮮政府というのは予測不能な動きをしています。しかし、北朝鮮政府も、韓国を攻撃してしまえば破滅的な結末に至るということは、ある程度、想像がついているはずです。もう何十年にわたって、米国は「もし、北朝鮮が韓国に攻撃をしかければ、韓国と一緒に反撃をする」と明確に表明しています。そうなれば、北朝鮮にとっては破滅的な状況が引き起されることは誰にとっても明らかです。米国は、強力な軍事力によるプレゼンスで北朝鮮に対する抑止を働かせようとしてきたし、現に機能しています。
一方、台湾の状況は大きく異なります。30年前ならば、誰もし台湾をめぐって戦争が起こるとするならば誰が勝つかということは、中国にとっても、台湾にとっても、米国にとっても明白でした。しかし、今はどうでしょう。誰もが自問自答せざるを得ない状況になっています。戦争が起これば、誰が勝つのか徐々にわからなくなってきているわけです。
こうした状況下では、状況のバランスが小さく変化するだけで当事国たちの行動に大きな変化が起こります。中国の指導部は、米国が台湾を助けに来ないだろうと見れば、エスカレートする方向に冒険に出てくる可能性があるということです。例えば、中国が台湾海峡の封鎖を試みることに対して米国がこれを止めることができない見た場合、あるいは中国が台湾に上陸して支配を試みることに対して米国がこれを止めることができないと見た場合、中国は打って出てくるでしょう。台湾を巡る米中の軍事力のバランスは、今、非常に不透明な状況になってきており、そこに不確実性が生じています。台湾海峡を緊張の本質はここにあると思っています。
若林 やはり台湾ですね。世界にとって台湾の重要性は大きく2つあります。1つは、地理的な位置です。米国にとっては中国が太平洋に漕ぎ出すのを阻む一線として、あるいは中国にとっては有事があっても米国の介入を許さない最終防衛ラインとして、第一列島線の一部を台湾が構成しており、しかも「1つの中国」に属しながら米国の影響下にあるというその特異な地政学的な位置です。そしてもう1つは、TSMCを含む、半導体を始めとした高度なテクノロジーの集積です。これは、西側諸国、特に米国のIT産業や防衛にとって欠かせない重要性を持っています。
ミラー 米国は、台湾に対しては明確なコミットを続けています。例えばジャック・キルビーがテキサスの研究室でまさに半導体の発明に熱中していたまさに同じ時に、ドワイト・D・アイゼンハワー大統領は第2次台湾海峡の危機に対して「台湾を守る」ということを表明しています。半導体があるからということではなく、米国はずっと台湾にコミットしてきているのです。しかしながら、台湾の人々の多くは、「シリコンの盾」があるからこそ、米国は台湾を守ってくれる、助けに来てくれる——半導体産業こそが台湾の安全保障のカギだと思っているようです。
私は、現実はむしろ逆ではないかと見ています。台湾に、世界的にも重要かつ不可欠な半導体産業、エレクトロニクス産業が集積していることは、台湾の運命にとって逆の効果を持ってしまうのではないかと思うのです。
台湾有事において最も起こる確率の高いシナリオは、中国が台湾を封鎖するというものだと思っています。その未来を想定するのであれば、台湾の半導体生産が世界にとって不可欠な重要性を持っていることが台湾にとって助けになる、ということは、そこまで自明ではないと思うのです。中国の封鎖に対して、台湾が米国に対して封鎖を解くべく助けを求めたとします。しかし、米国にとって封鎖を解こうとするということは戦争が起こるリスクにもつながりかねません。台湾に重要な半導体産業拠点が集中していることにより、その戦争は半導体のサプライチェーンそのものにも大きな負荷をかけることになります。米国の半導体産業にも大きなコストがかけることになるでしょう。米国は、その膨大な経済コストの負担を負ってまで、台湾の封鎖を解くために援助に行くでしょうか。私はその問いに対する答えはそれほど明白ではないと思っています。つまり台湾は、実は半導体サプライチェーンに果たす役割がそれほど大きくない方が、台湾自体にとってはより安全なのではないかと思うのです。
しかし、台湾の人たちはそのことを認めたがりません。台湾政府は、やはり「シリコンの盾」という政策を守っていくという道を選び続けるのでしょう。
若林 そのジレンマは、過去10年間、段階的に、想像を超えて、あまりにも深く世界の半導体産業が、台湾に位置するTSMCという1社に依存してしまったことで、より解きがたいものになっているように思います。それこそが日米が最も頭を悩ませる現実ですね。
ミラー その通りだと思います。ここ10年、半導体産業におけるTSMCの果たす役割は拡大し続け、同時に、台湾海峡における中国の軍事力も増大し続けました。この2つが同時に進んだことが、日米を初めとする各国政府にとって懸念材料になっています。
やらなければならないこと2つあるかと思います。1つは、半導体産業を台湾から動かすこと。2つ目は、台湾海峡における抑止を、もう一度、復活させるということです。現実的にはどちらも難しいと思います。けれど、両方を追求していかなければならないと思っています。その2つの組み合わせが、やはり望ましい結果を生むのだと思います。
半導体の議論をしていると見失いがちになりますが、根本的な命題は、中国が台湾に攻撃を仕掛けることをいかに抑止するかということです。米国政府も、日本政府も、この5年間はその命題に向けて、半導体政策のみならず、軍事的な政策にも視線を配ってきました。米国政府も、ある程度、立場や政策を変えてきたと思いますが、とりわけ大きく変わったのは日本でしょう。革命的なかたちで安全保障政策を変えてきました。その変化は、やはり台湾に対する中国の脅威が増しているということに照らして生じているものだと思います。
そしてまた、それでもなお、抑止政策を成功させるのはなかなか難しいと思います。

若林 こうした米中の台湾を巡るにらみ合いが続けば続くほどに、「シリコンの盾」の強度が増すどころか、TSMCがアリゾナや熊本に工場を新設するなど半導体産業が台湾の外に出ていく、あるいはラピダスのような新しいプレーヤーが台湾の外に登場することによって、皮肉にも米国にとっての台湾の重要性が下がっていく——。この台湾が抱えるジレンマが、台湾海峡における米中の力関係、ひいては日本の将来にどのような影響を及ぼすのか。クリスさんとの半導体をめぐる対話を通じて、改めて日米が直面する難問を実感しました。ありがとうございました。
ミラー ありがとうございました。(了)
クリス・ミラー(Chris Miller):1987年米国イリノイ州生まれ、マサチューセッツ州ベルモント在住。タフツ大学フレッチャー法律外交大学院国際歴史学准教授。フィラデルフィアのシンクタンク、FPRI(外交政策研究所)のユーラシア地域所長、ニューヨークおよびロンドンを拠点とするマクロ経済および地政学のコンサルタント会社、グリーンマントルのディレクターでもある。ニューヨーク・タイムズ、ウォール・ストリート・ジャーナル、フォーリン・アフェアーズ、フォーリン・ポリシー、アメリカン・インタレストなどに寄稿し、新鮮な視点を提供している気鋭の経済史家。ハーバード大学にて歴史学学士号、イェール大学にて歴史学博士号取得。
若林 秀樹:東京理科大学教授。1984年東京大学工学部卒、86年東京大学大学院工学系研究科修了、野村総合研究所入社。欧州系証券会社、JPモルガン、みずほ証券ほかでアナリストを務める。日経新聞アナリストランキングで1位5回(電機部門)。2005年、日本株運用のヘッジファンドを設立し最高運用責任者に。2017年より現職。「半導体・デジタル産業戦略検討会議」「デジタルインフラ(DC等)整備に関する有識者会合」の有識者メンバーで。「電子情報技術産業協会」(JEITA)半導体部会の政策提言タスクフォース座長も務める。
地経学の視点
半導体は、民需から軍用にいたるまで、もはや石油などと同等と言っていい不可欠性を握るが、地下資源と異なるのは、企業と「技術」や政府の「政策」によって——つまり、人間の意思と力によってその偏在性が移ろうという点だ。日本が敗れ、韓国が台頭し、台湾にTSMCが生まれ、いま米中が互いにその偏在性を奪い合おうとしている半導体の歴史は、その前提のうえに現在進行形で記述されている。両氏は本対談を通じて、その最先端と未来を探り合った。
トランプ政権に半導体の戦略性を気づかせたのはむしろ日本だったとミラー氏は言う。若林氏は、日本の半導体政策のかつてない規模とスピードを指摘した。霞が関や永田町でも「最後のチャンス」という言葉が多用されている。半導体が、失うことが許されない戦略分野であることは間違いない。
だが、だからこそ、私たちは、日本がかつて半導体で「敗戦」を喫したという事実と正面から向き合う必要があるということは指摘しておきたい。対談中、両氏からは、外的要因として日米貿易摩擦、内的要因として日の丸DRAM業界の驕慢と不毛なシェア争い、日本の産業政策の不在など、様々な「敗因」が挙げられた。全く同じ要因は今はない。だが、政策や技術の変遷によって半導体業界に顕著に起こるゲームチェンジに対して、日本勢は過去の延長線上でしか未来を描くことができず、幾度となく競争の軸をずらされて取り残された。その体質が変わっていなければ、また別の環境変化に対しても同じ轍を踏む可能性がある。
「やるからには資源投下は大胆に」「ここで手を打たなければ100年は取り返せない」——。一面でそれも正しいが、また同時に、かつての失敗を検証して失敗を繰り返さないための冷静な目も必要だろう。わずか数十年に過ぎないが、今まさに猛烈な勢いで書き加えられ続け激動を続ける半導体の世界史をどう読み、そこから何を学ぶのか。本対談には多くのヒントがあった。TSMCの誘致からラピダスの設立まで、日本のチャレンジはこれから正念場を迎える。実業之日本フォーラムでは、その挑戦を検証しながらお伝えしていきたい。(編集部)