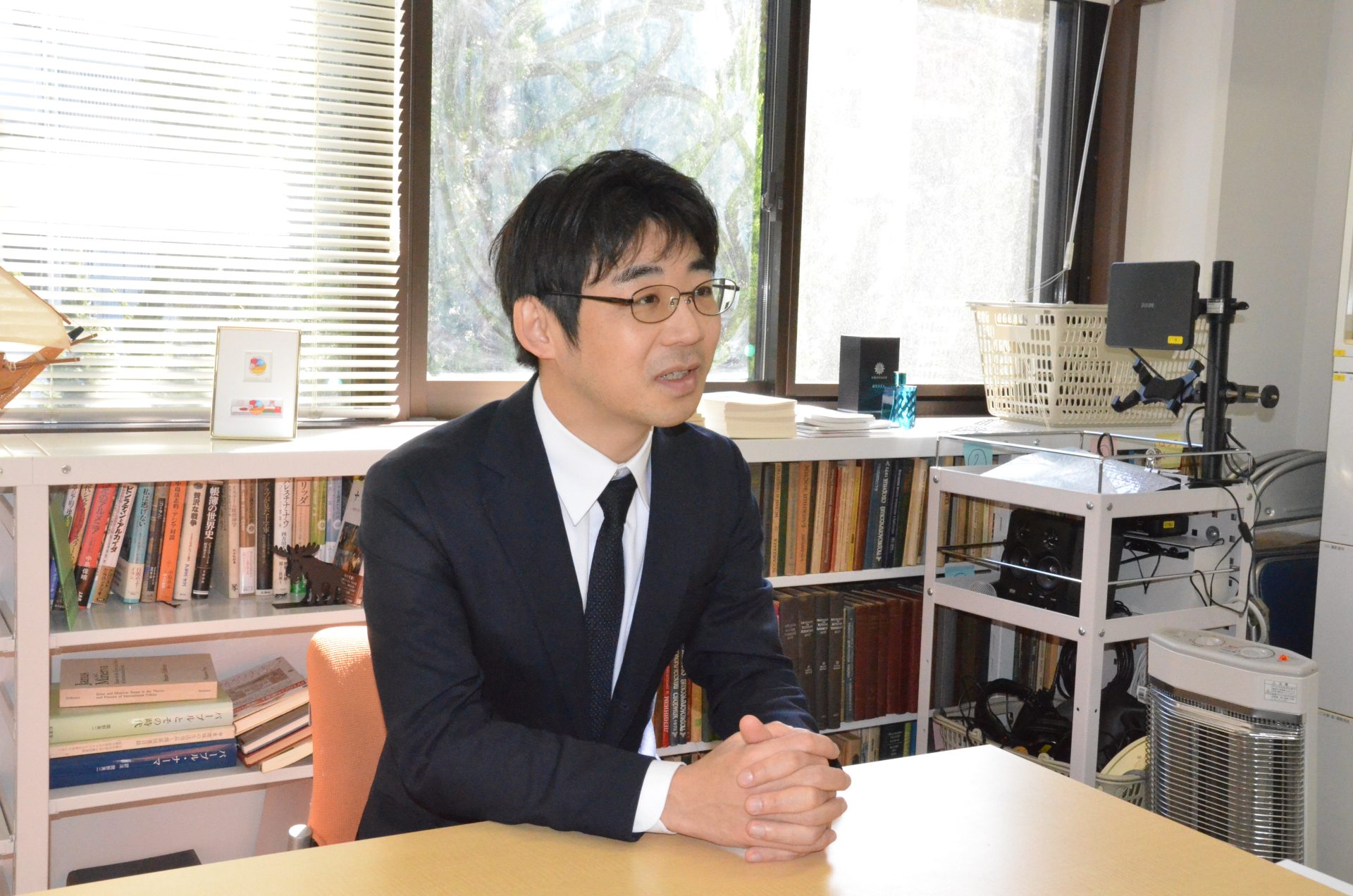中国では習近平国家主席への権力集中が進んでいる。習氏は、権力の過度な集中を防ぐため「2期10年」と定められていた国家主席の任期制限を撤廃し、2022年秋に3期目を果たして側近をイエスマンで固めた。
強権政治の正統性を担保するのは、GDP世界第2位の経済大国としての自信だ。習政権は「中国の特色ある社会主義」を掲げ、市場経済と統制経済の両立という特異なビジネスモデルを推し進める。一方で、足元では不動産不況に伴う不良債権問題で経済が減速し、国民の不満が高まっている。
果たして中国は新たな覇権国となるのか、あるいは衰退するのか。中国の政治と経済を長年ウォッチしてきた東京財団政策研究所主席研究員の柯隆(かりゅう)氏に語ってもらった。
※本記事は、2023年12月13日開催の「地経学サロン」の講演内容をもとに構成したものである。(構成:鈴木英介=実業之日本フォーラム副編集長)
習政権は3期目入り以降、ますます強権化し、国際社会との軋轢(あつれき)もいとわないようにみえる。その背景の一つには、習政権の現執行部の思想がある。彼らは毛沢東が発動した文化大革命(1966〜76年)で青春時代を過ごした世代だ。文革では「造反有理」、つまり体制に逆らうことには道理があるというスローガンの下、教師や文化人など知識人をブルジョア思想だと決めつけて迫害した。彼らは「自分こそルールだ」と思い込み、既存の国際社会のルールを認めず、自分たちに従わせようというメンタリティーを持っている。
そして彼らの自信は、過去30年あまりの経済成長によって裏付けられている。かつて中国は市場開放政策をとり、外国資本を積極的に受け入れた。特に、日本の貢献が大きかった。1970〜80年代の日本人経営者は、中国へのある種の憧れがあった。孔子、孟子、論語を積極的に学んだ世代で、中国文化に強い影響を受けた。また、過去の侵略行為で中国に迷惑をかけたという気持ちもあって、中国の経済発展にできる限り貢献しようとした。そのシンボルが、日本企業の協力の下、78年に着工した上海の宝山製鐵所だ。当時の新日鉄を中心に、実質的に技術供与して作られた。他にもナショナル(現パナソニック)が中国にブラウン管工場を作ったり、家電の技術を供与したりし、中国経済の向上に大きく貢献した。
米国の協力も大きい。今でこそ米中は対立しているが、1980年代、米国は中国から多くの留学生や技術者を受け入れ、米国で学んだ文化や科学技術を持ち帰って中国の経済成長に貢献してもらおうとした。国際社会が中国を受け入れて成長すれば、彼らはおのずと民主化・自由化するだろうという一方的な期待をもっていたからだ。これは後に「エンゲージメントポリシー」と呼ばれた。おかげで中国は成長したが、途中で文革世代が実権を握るようになると、国際社会とのエンゲージメントどころか、非協調的な「戦狼外交」をとるようになった。日本にとっても欧米にとっても想定外の展開だ。
「狼」から「パンダ」に?
習政権は「中国の特色ある社会主義」という政策を掲げている。いわゆる国家資本主義、統制経済と市場経済の組み合わせによる中国独自のビジネスモデルだと言われているが、市場経済は副次的なものだ。習主席は「統制経済でも国を強くできる」という、ある種の妄想を持っている。
統制経済の例としては、民間企業の参入障壁が挙げられる。中国では、重厚長大産業や公共部門など、経済の要となる産業は全部国有化することになっている。そして、民営企業は国有企業が手がけていない新分野、例えばeコマース(電子商取引)やSNSといったIT事業を担う。その典型はITプラットフォームとなったアリババだ。
しかし、中国の民間ITプラットフォームはあまりにも巨大化してしまった。例えばアリババグループは、傘下企業を通じて融資仲介事業を始め、国有銀行が仕切る金融分野を侵食した。政府はそれを許さず、同グループに対し独占禁止法の名目で巨額な罰金を科した。
習主席は国内向けに「国有企業をより大きく、より強くしていく」と呼びかけているが、このスローガンには無理がある。国営企業を大きくすることは簡単で、政府が主導してM&Aを進めればよい。だが、規模を大きくしても収益性が上がらなければ強くはなれない。国営企業だけで国力を強くできるのなら、鄧小平政権は改革開放政策をとらなかったはずだ。
結局、統制経済と市場経済は両立できない。10数年前に中国GDPが2桁成長したころの蓄えで、「中国の特色ある社会主義」が成立しているかのように強がっているに過ぎない。だが、その蓄えも底が見えてきたようだ。習主席は2023年11月、APEC(アジア太平洋経済協力会議)に参加するためにサンフランシスコを訪れ、バイデン米大統領に会った。その際、強気な「戦狼外交」は影を潜め、ほほえみの「パンダ外交」に軟化していた。習主席自身、中国が成長しなくなったことを実感しているのだろう。
中国が成長を続けていくには何が必要か。一つは、民間企業が成長しやすくなるようなマーケット環境の整備。もう一つが、これまで中国経済を牽引してきた外国資本の呼び込みだ。外国資本と中国の安い労働力を組み合わせて安いモノをたくさん作り、輸出して外貨を稼いだが、今は外国資本が続々と逃げている。中国国外への工場移転が進んでいることに加え、政府の民間企業への締め付けが厳しいからだ。中国経済を支えてきた「2本の柱」が、いずれも折れそうになっている。
それを実感している習主席は、2023年11月にサンフランシスコでバイデン大統領に会った後、ウォールストリートの大企業CEOとの夕食会に参加し、「中国は皆さんにとって有望な市場環境ができている」とアピールしたが、信用されていない。中国政府が「反スパイ法」を恣意的に運用するリスクがあるからだ。同法は23年7月に改正され、取り締まりの対象となる「スパイ行為」の定義がより広く、曖昧になった。中国でビジネスを展開するに当たり、どのような行為が同法に抵触するか不透明だ。日本の企業も、アステラス製薬の社員が同法違反の容疑で中国当局に拘束されたままだ。習政権が持続的な成長を目指すのなら、市場メカニズムに任せ、法にのっとってルール化していくべきだが、完全に逆行している。
テック企業に潜む「隠れ国営企業」
国営企業を優遇し、民間企業を圧迫する現象は「国進民退」と呼ばれるが、実は、中国政府によるテック企業への締め付けは一様ではない。先ほどアリババグループが罰金を受けたと述べたが、同じくIT大手であるファーウェイへのスタンスは穏やかだ。おそらく政府がバックについているのだろう。
ファーウェイの創業者の娘で、同社CFO(最高財務責任者)である孟晩舟氏は2018年、米国から詐欺などの容疑で起訴され、カナダで拘束された。中国政府はカナダ政府に強く抗議し、報復のようにカナダ人を拘束した。孟氏は無罪を主張しつつ、米司法当局との司法取引に応じたことで釈放された。中国政府は直接の関連を否定したが、孟氏の釈放後、カナダ人を解放した。
孟氏が解放されたとき、中国政府は彼女のためにチャーター機を派遣した。いくら巨大企業だからといって、一民間企業のCFOのために政府がチャーター機を用意するのは不自然だ。ファーウェイ以外のビッグテックは成長するにつれ、国有企業を脅かす存在となり、罰金などで締め付けられている。しかし、同じように成長しているのに、中国政府は同社に対する罰金は科していない。ファーウェイ自身は「われわれは民営企業だ」と主張しているが、非上場であり、資本関係は不透明だ。実質国営とまでは言い切れないが、創業者の任正非CEO(最高経営責任者)が人民解放軍出身であることも勘案すると、少なくとも「普通の民営企業」ではないと言える。
「デジタル・レーニン」最大の被害者は…
習政権は、デジタル技術の発達を統治に活用している。監視カメラやスマートフォンを通じた個人情報取得も可能となり、デジタル技術による監視社会が現実のものとなった。ドイツの政治学者セバスチャン・ハイルマンが「デジタル・レーニン」と名付けたデジタルによる強権的な統治手法は、自由・民主を価値観とする西側からすると受け入れられない概念だが、中国政府からすれば、不満分子を抑え込み、社会の安定に資するというわけだ。
ジョージ・オーウェルの小説『1984年』では、「ビッグ・ブラザー」という独裁者が人々を完全な監視下に置く社会が描かれた。3年間の新型コロナウイルス禍を経て、中国は『1984年』の世界をほぼ実現させた。政府は、感染拡大防止のため、人々の移動を制限する装置としてスマホを活用した。個人を位置情報から特定できるようになったし、発信する情報も監視されている。海外のSNSに書き込んだとしても、公安当局には知られてしまう。
ただ、デジタル・レーニンの最大の被害者は、共産党の幹部たちだ。例えば昨年、行方不明になった2人の高官がいる。1人が国防大臣、もう1人が外交部長(外相)だ。汚職がらみと言われているが、彼らは当局に監視されていた。当然デジタル技術も使われていたはずだ。
日本のマスコミはほとんど報道していないが、米国の政治専門サイト「ポリティコ」の報道によると、行方不明になった者のうち、秦剛国務委員兼外相は、昨年7月には既に殺されていたか、拷問死していたという。正式発表はないが、こうした報道に接して一番恐怖を感じるのは、庶民ではなく共産党幹部だ。「自分が失脚したら、彼と同じ運命をたどる」ということを思い知らされた。幹部のプライバシーさえ尊重されないような行き過ぎたデジタル監視社会は、いつか必ず引っくり返される。
不良債権は統制経済の副産物
中国では、不動産バブルが崩壊し、不良債権問題が深刻さを増しているとよく言われる。確かに不良債権は、銀行が抱えているものだけで約3兆元(約62兆円)あるとされる。銀行よりも規制が緩い「シャドーバンク」と呼ばれる非銀行金融や、地方政府傘下のインフラ投資会社「融資平台」が抱えているものまで含めると、総額は100兆元(約2000兆円)にも及ぶというIMF(国際通貨基金)の試算もある。
だが、不良債権は金額の問題ではない。問題の本質は、国有銀行に不良債権を引き当てる資産があるかどうかだ。不動産融資における債権回収はそれほど難しくない。担保にとった不動産を差し押さえて、競売すればある程度回収できるからだ。だが、国有企業の債権は差し押さえができない。貸出先に政府の後ろ盾があるからだ。
通常、中央銀行は景気の変動に対応して金利を上8げたり引き下げたりして金融政策を行う。中国の景気は急速に悪化しているので、本来は金融緩和がセオリーだ。しかし、中国は金利をそれほど下げていない。事実上の政策金利に当たる1年物の最優遇金利(ローンプライムレート、LPR)は、いまだに3%台にとどまる。
中国の中銀が金利を下げ渋っている理由は、中国の市中銀行のほとんどを占める国有銀行への配慮だ。中国の国有銀行は、手数料ビジネスを主とする欧米の銀行とは対照的に、利ザヤ(貸出金利と預金金利の差)で稼ぐビジネスモデルだ。中国の中銀である人民銀行は、銀行貸出金利の指標となるLPRをなるべく高めに維持し、銀行の利ザヤ確保に貢献している。そして、利ザヤの一部は不良債権に対する引当の原資となる。
国有銀行の不良債権のうち、不動産の焦げ付きは近年表面化したもので、金額はさほどではない。一番多く不良債権を生み出しているのは、国有企業への貸し出しだ。国有企業は概して非効率な経営を行っており、彼らに融資する返済が滞りがちになる。しかし、国有企業には行政の後ろ盾があるから「返せ」と言えない。こうしたことから中国は、景気が悪化しても低金利政策をとれない。ある意味、不良債権問題は統制経済の副産物だ。
今までの中国の成長は改革開放のおかげであり、現下の閉鎖的な経済政策は持続可能ではない。ハーバード大学の教授が著した『国家はなぜ衰退するのか:権力・繁栄・貧困の起源』(ダロン・アセモグル,ジェイムズ・A・ロビンソン著)は、国家が繁栄する前提は「包容力」だと主張する。例えば米国の強さは、多様な考え方を受け入れ、切磋琢磨することでイノベーションを生む土壌が整っていることにある。中国にも有能な人材は多いが、異論を認めない習政権はそうした活力を殺している。
このままいけば、中国は北朝鮮のような閉ざされた恐怖国家になる。しかし、北朝鮮と違い、中国の人々は、少なくともこの40年間、市場開放による自由や豊かさを味わった。もう1度貧しい社会に戻ることは誰も受け入れない。いずれ中国は、改革開放の路線に舵を切らざるを得ない。
写真:新華社/アフロ
柯 隆:東京財団政策研究所 主席研究員
1963年中華人民共和国・江蘇省南京市生まれ。88年来日、愛知大学法経学部入学。92年同大卒業。94年名古屋大学大学院修士課程修了(経済学修士号取得)後、長銀総合研究所国際調査部研究員、富士通総研経済研究所主席研究員などを経て2018年から現職。著書に『「ネオ・チャイナリスク」研究』(慶應義塾大学出版会、21年)ほか多数。
地経学の視点
グローバル経済の申し子として目覚ましい成長を遂げた中国は、しかし西側が期待したような民主化の波に呑まれることはなかった。むしろ経済成長を裏付けに強権国家としての色あいを強め、「自由・民主」という価値観に対抗する西側のライバルとなった。習政権は「デジタル・レーニン」で人々を政府の監視下に置き、香港の民主主義を担保する「一国二制度」を骨抜きにし、経済力でグローバルサウスを自陣に引き込もうとしている。
他方で、行き過ぎた権力集中は国を弱くする。政策の誤りを指摘できず、市民や市場と対話しないため、社会的・経済的ショックが起きると、ハードランディングに陥りがちだ。コロナ禍対応に伴う苛烈なロックダウンで経済低迷を招いたかと思えば、今度は唐突な「ゼロコロナ解除」で感染が再拡大。政府の救済を受けられない民間の中小企業が倒産して若者の失業が急増し、マイホームが売れなくなった。このことが中国の不動産バブル崩壊の一因とされる。
「現場の声」が上がってこない政府では、危機の共有が遅れるため、一気に社会が混乱することはない。だが、崩壊はゆっくりと確実に進み、局所危機が線となり、面となれば革命が起きる。中国がそれを避けるには、国際社会に非協調的な強権主義を改め、再び改革開放に転換せざるを得ない。「結局のところ習政権のビジネスモデルは持続不能だ」と柯隆氏は言う。
とはいえ、中国の政策転換のタイミングは誰にも分からないし、時機を逸すれば中国発の金融危機が起こらないとも限らない。各国は中国に対する過度な経済依存を低減させる「デリスキング」を進めているが、これは中国の膨張主義に歯止めをかける戦略であるのと同時に、サプライチェーンの分散を図ることで中国崩壊のダメージが国際的に及ばないようにするための手段とも言えるだろう。(編集部)