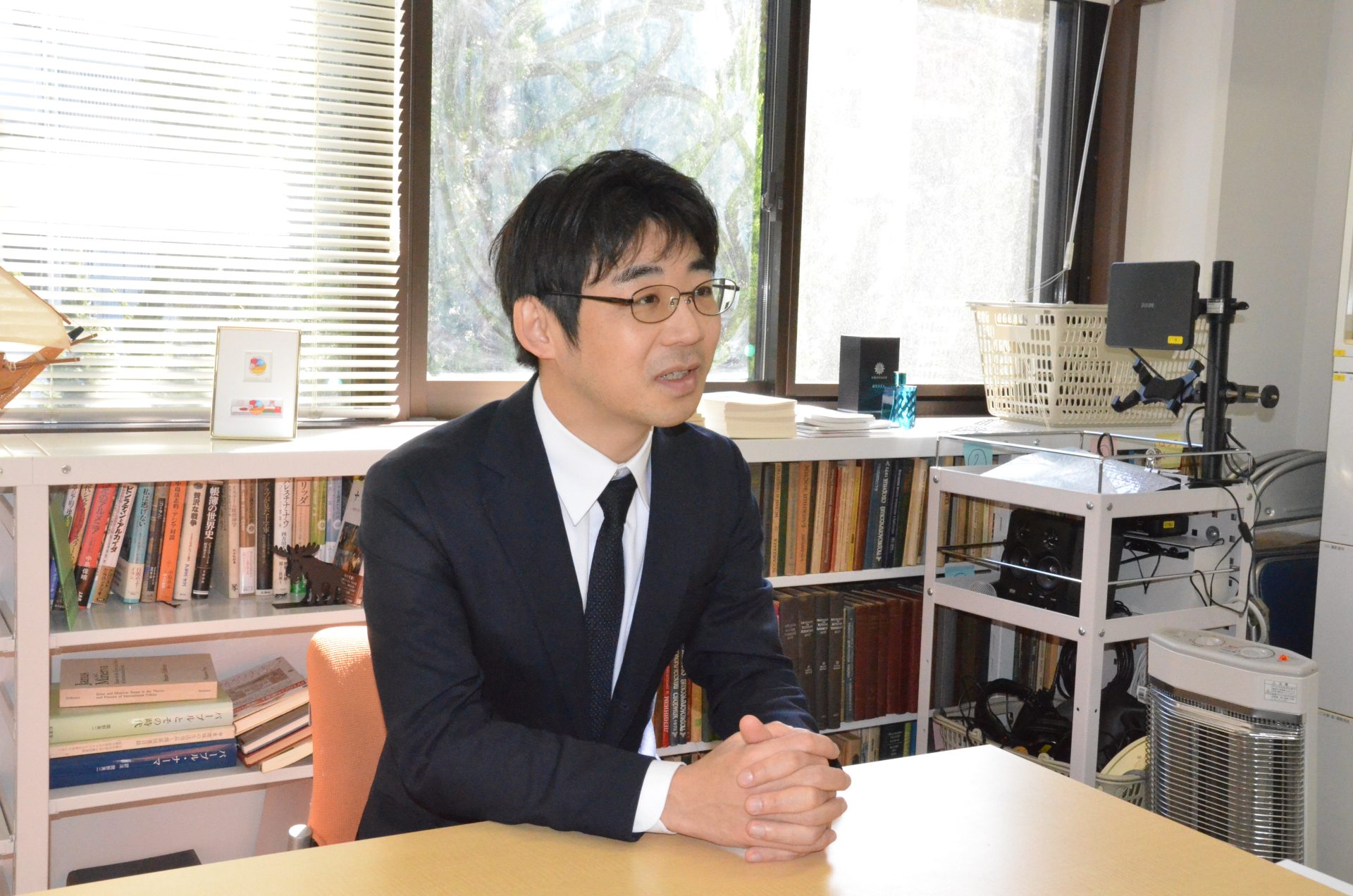国際的な供給ショックが続き「食料安全保障」が叫ばれるなか、日本にはどのような構造的問題があるのでしょうか。前回は、農林中金総合研究所の平澤明彦理事研究員へのインタビューを通じて、日本の農政の経緯や課題を見てきました。引き続き今回は平澤理事研究員に、食料安保を確保するための具体的な施策について聞きました。(聞き手:鈴木英介、白幡玲美)
――コロナ禍やウクライナ戦争は、食料安全保障上どのようなリスクを引き起こしていますか。
コロナショックとウクライナ戦争に分けて整理したい。まずコロナ禍で明確になったことは2点あり、一つは「サプライチェーン(供給網)を長くするほどリスクが高まる」ということ。国際的なサプライチェーンにおいては、どこか1カ所で鎖が切れたらモノがこなくなることが再認識された。コロナ禍ではEUの一部の国が国境を閉ざす事態になり、域内市場でも混乱を招いた。
もう一つは、今のところ日本の課題とは直接の関連はないが、2000年代以降、削減を進めてきた飢餓人口が元に戻ってしまったことだ。コロナ禍の2年ほどで1億5000万人も飢餓人口が増えた。今回はこれまでの食料危機とは様相が異なり、デフレ的な要因による。つまりロックダウンなどの影響で就業機会が減り、所得が落ち込んで食べ物が買えなくなった。08年のリーマンショックは富裕国を中心とした金融危機であり、食べ物がなくて死ぬことはあまりなかった。しかし、コロナ禍は世界の人々に影響を及ぼし、しかも経済力が弱い人ほどダメージを受けた。やはり購買力は重要だ。
次にウクライナ戦争の影響だが、これも二つのリスクが顕在化したと考えている。一つは「不足は輸入でまかなえばよい」という考えが戦争によって否定されたことだ。貿易は平和が大前提だ。冷戦が終わり、平和を維持しようという国際的合意がその担保になると思われていたが、残念ながらその考えは正しくなかった。
二つ目は、戦争が起きた際の影響の大きさだ。特にウクライナ戦争では、ロシア・ウクライナとも主な食料輸出国だったことに加え、ロシアが世界最大の肥料輸出国だったのでさらに影響が広がった。また、ロシアにはさまざまな経済制裁が科されているが、制裁に参加している西側諸国の企業が世界の貿易を担っているために影響が大きい。ロシア産肥料の輸出先が新興国や途上国の場合、その国は制裁に参加しなくとも、西側企業はレピュテーションリスクを考えると、ロシア発の取引に船や金融のサービスを提供できない。そのため、世界の商流に影響を及ぼすことになる。
さらに、ロシアが貿易統計を公表しなくなったために、モノの流れが見えなくなってしまった。途上国では月次でデータを公表しない場合が少なくないし、年次のデータも信頼性が低いことがある。国連のデータと突き合わせると、輸入側である新興国・途上国が公表しているデータと、輸出国のデータが整合しないこともままある。2022年度は、小麦の主要輸出国のうちロシアが豊作だったが、その割当先は不明だ。戦争は、当事者でなくとも輸入国に不利な事態を引き起こすということだ。
マクロの視点を欠く市場原理優先の農政
――食料安保の観点からも有事への備えの重要性が増すなか、日本は農地の不足と水田の過剰という構造問題を抱え、足りない農地が耕作放棄されるのが実情です。どのような政策を取るべきでしょうか。
国内農地は貴重な資源であり、マクロの政策目標として「農業生産力の維持」を掲げるべきだ。前回触れたとおり、「食料・農業・農村基本法」は、特定品目の保護・振興ではなく、市場原理を優先している。自由貿易の下、競争力のある農業を育てようという方針でやってきたが、それはミクロの政策だ。
現行基本法の下で展開された政策は、個別の農家の経営をいかに強くするかということと、地域の衰退は農家の衰退につながるので地域を支えようというもので、特に前者の効率的経営中心の考え方だ。だから付加価値を高めるとか、差別化しようとかという話になる。だがこれは「量」の話ではない。高付加価値で高く売ることを推奨してきたが、その間に農地はどんどん減っている。
「農家が稼いで食べていくことができる」というミクロ的な話と、「すべての国民が十分に食べていくことができる」というマクロの話は意味が異なる。今の農政の施策は「生産基盤の強化」というマクロ的な観点が弱い。
問題は、なぜ競争力と差別化中心の農政になっているかということだ。それは、輸入自由化によって安い輸入品との競争にさらされ、国内生産は付加価値を高めて差別化することになったからだ。しかし、こうした方向で努力するほど高級品の域に追い込まれ、マスマーケットの消失、すなわち生産力が落ちることにつながる。こうした構図にある以上、「量」の部分に再びフォーカスするには、政策の支えが必要だ。
例えばスイスは、日本と同様、1990年代からの貿易自由化と農政改革で農地が縮小したため、国内農業生産を支える政策を強化した。国内で生産しているカロリー量や農地面積などを基準に、中期の農政計画で目標を定め、事後評価も行っている。緊急時に2300キロカロリーの食料を確保するために必要な優良農地の面積を計算し、その面積を各州に割り当て、各州が基礎自治体に細分化し、その維持を義務付けた。優良農地を転用した場合には、他の農地を改良して同じだけの生産性を維持することになっている。さらに、スイス政府は市場価格とは切り離して、生産者に直接補償する「直接支払い」という制度を設け、特に農地での生産維持に多くの予算を充てた。
日本は、農地不足・コメ余りのなか、小麦やトウモロコシなど「土地利用型作物」の生産が本格的に拡大しない状態が50年も続いている。にもかかわらず、今の基本法の枠組みには「日本全体として限られた農地をどう利用していくのか」という具体的なビジョンと施策がない。スイスでは「直接支払い」の抜本的改正を行うまでに8年かけた。日本も各部門から広く知見を集め、5年、10年かけて議論すべきだ。
所得補償で品目転換、米価引き下げで需要喚起も
――農業生産を維持・拡大するにはどのような政策が考えられますか。
土地利用型作物の収益性を向上させるため、直接支払いなどの支援が必要だ。具体的には大きく三つの施策が考えられる。
一つは水田を畑に転換して、輸入している小麦・大豆・トウモロコシや、それ以外の代替品目を作ることだ。問題は、内外価格差が大きい(輸入品が安い)ことに加え、日本の気候風土がそれらの穀物の育成にマッチしていない、あるいは日本に合わせた技術が確立していないことで、継続的な助成金がないと転換後の維持は厳しい。
また、日本で水田を畑に転換しようとしても、農家単独ではできない。水田は、その維持管理を行う組織「土地改良区」による投資の下、水利でつながっているので、地域の農家全員が参加してくれないと転換できず、零細な農家も含めなければならない。そうした人をのけ者にしてしまうと地域での合意形成は図れないだろう。
半面、水田を維持し続けることには畑よりも多くのコストがかかり、その財源の多くは税金だ。長期的な財政コストの面からも「水田か」「畑か」という議論はするべきだろう。コメは単収が安定しており、水田の治水機能など利点も多い。十分な検討が必要だ。
二つ目に、輸入品目の国内生産拡大ではなく、コメ余りの状況を解消し、農地維持を図るために「コメをもっと活用する」という視点だ。
検討が進んでいるのはエサに使うことだ。ただ、エサ用ならトウモロコシを原料にした方がコストは低くすむ。もし水田でコメとイネを原料にエサを作るなら、どうして水田でやらなければならないのか、理由と説明が必要だろう。また、米粉にしてパンを作るなど、コメを加工して消費を増やすアイディアもあるが、米粉にするためのコストが高い。米粉の特性を生かした需要はあるかもしれないが、それは量の政策とはいえず、ニッチなものだ。
第三の道として、やや乱暴かもしれないが、「もっと国民に食用米を食べてもらう」という方法もある。これはずっと農水省が推進してきた政策だが、コメだけ守って高値を維持しようとしてきたから実現できていない。公定価格をやめてから米価は大幅に下がったが、まだ小麦より高い。これを逆転させればコメの消費が増え、米価が下がり、コメ余りの解消につながる可能性がある。
また、小麦の価格が高くなれば、コメ農家に土地利用型作物への転換を促す効果も期待できる。もちろん価格が下がれば、一定程度コメ農家への補填が必要だ。その下げ幅は、消費者だけでなく、中食や外食、加工メーカーの需要を踏まえるべきだ。意向調査も重要だし、試験的に安く売るといった取り組みも考えられる。
他方、コメの価格は相対的に下がればいいので、小麦の値段を上げるという手段もあるが、貿易ルールの制約があり難しいのではないか。むしろTPP(環太平洋パートナーシップ協定)や日欧EPA(経済連携協定)で輸入小麦の国内価格は引き下げの予定だ。
EUはかつて直接支払いで穀物価格を下げ、飼料向けの需要を拡大した。「所得補償+コメ価格引き下げ」でどれだけコメの消費が増えるか、検討する価値はあるのではないか。「第三の道」もコストはかかるが、エサにするよりは1ヘクタール当たりの財政負担は小さいと思われる。主食用米全体に適用するためのコストは面積に応じて大きくなるので、考え方の整理が必要だ。
コメの値段を下げる際は、「受益者は農家ではなく消費者だ」という理屈で、補填の財源となる追加予算を新たに調達できるとよい。農家からすれば、所得を補填するのに、農水省の予算を削って消費者に渡すことになれば正味の割り当てが減るわけで、「外からの予算」が前提といえる。公定価格を決め、消費者が農家に補填する施策と違って、政府が農家に直接補填する「直接支払い」にはそうした性格が強い。EUでも、EU非加盟で独自の政策を有するスイスでも、直接支払いを導入するときは農業予算が何割か増えている。
コメの価格引き下げのために補填するか、水田から畑への転換(輸入品目への転作)に補填するかは制度設計次第だ。コストと効果を天秤にかけて、一品目ごとに精査し、できれば品目は農家が自由に選択し、合理的な「量」の拡大を目指すことが望ましい。
――農家への補償については議論が分かれます。かつての農業者戸別所得補償制度(後の経営所得安定対策制度)は、支給対象を大規模農家に絞らず、生産調整に参加する販売農家をすべて対象にした「バラマキ」だったのではないかという批判もあります。
誤解を恐れず言えば、農業政策とは基本的にバラマキだ。農業は市場構造が独特で、生産者がたくさんいて、しかも相対的に小規模であり、彼らに広くお金をまくのが農業補助金だからだ。「ごく小さい農家にまで補助金を渡すのはバラマキだ」と批判する声があるが、数の上では小規模農家が多数派だ。それに欧州では、「小さくて生産性が低く稼げない農家になら税金を投入してもよい」という論調だ。農地は借り手市場になっており、小規模農家の退出を急がせる必要性は薄れたのではないか。
兼業収入との兼ね合いもあるが、作り手が不足する中で小規模農家を排除すべきではない。一方、土地利用型農業では、規模の大きな専業農家の補助金への依存度が高く、彼らへの補助金を充実させなければ農業そのものを辞めてしまい、農地を維持できなくなってしまう。どの方法をとるにしても、前提として、どれだけの需要喚起効果があるかを中長期的に議論していかねばならない。農地維持の観点から現実的なバランスを探るべきだ。
平澤 明彦
農林中金総合研究所 理事研究員
1992年より農林中金総合研究所勤務。現在の主な研究分野はEU・米国・スイスの農業政策、食料安全保障政策など。2004年、東京大学大学院博士(農学)取得(論文博士)。