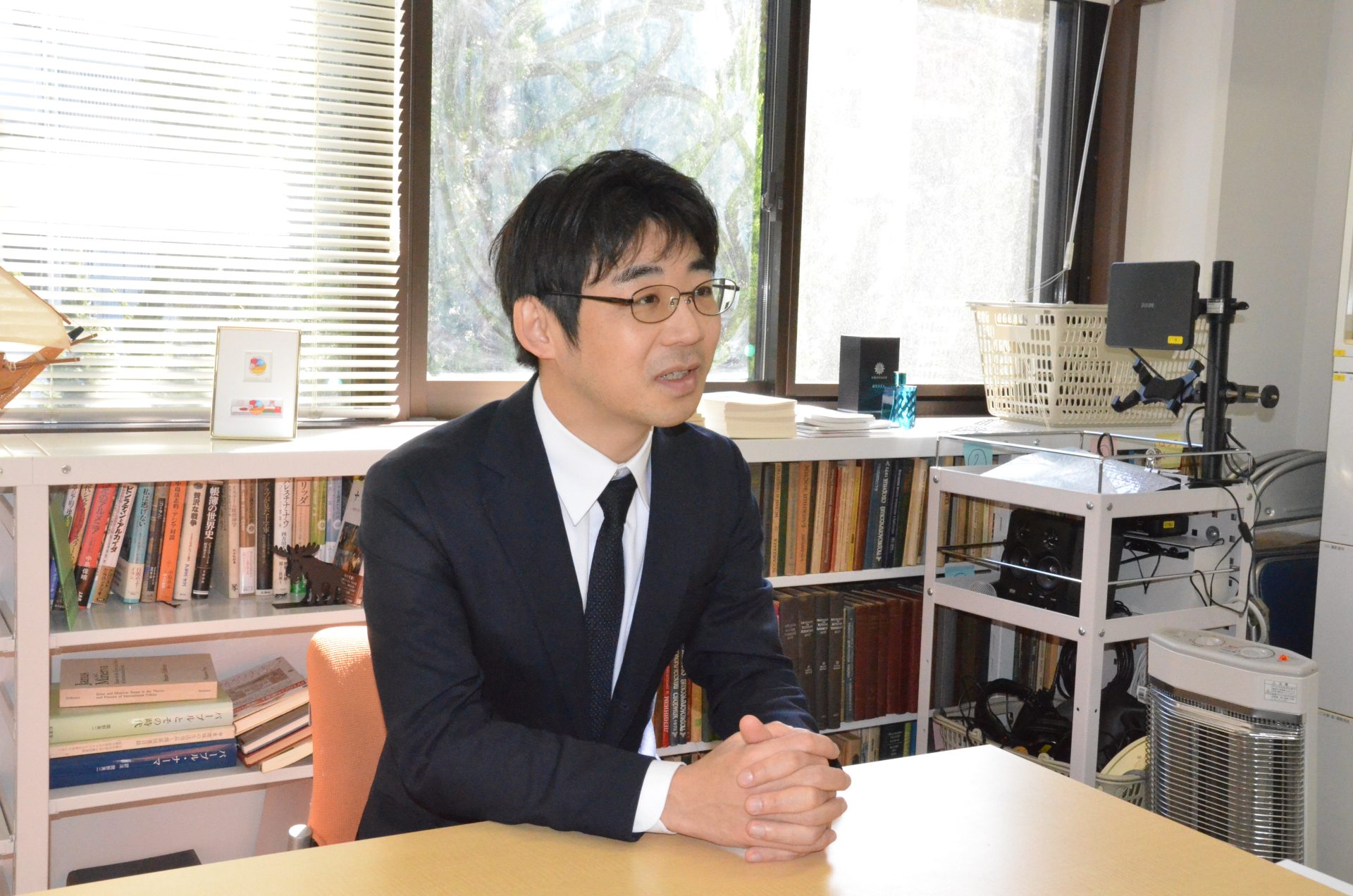中国不動産大手32社が「決算開示延期」
3月22日、流動性危機に直面する中国の不動産大手「中国恒大集団(こうだいしゅうだん)」傘下3社が、「事業環境の急変」を理由に21年12月期の通期決算開示の延期を発表し、世界に波紋が広がった。
中国恒大集団だけではない。香港市場に上場する多くの企業は決算報告書の締日を12月末に設定しており、そこから3か月以内の決算発表が義務付けられている。つまり3月末だ。
3月31日時点での21年の通期決算開示を延期した中国の不動産企業は32社に達した。そのうち14社はその理由を「新型コロナウイルス流行の影響による監査遅延」だと説明。帳簿の記載に関する取引先や金融機関への確認作業などの監査事務に遅れが生じ、期日どおりに開示できなかったというのだ。
今回延期を決めた不動産会社の資金繰りは悪化せざるを得ないだろう。また、中国の不動産市場に詳しい証券アナリストは、「中国の不動産会社のデフォルト (債務不履行)リスクが高まるなか、監査法人の会計士は平時に増して慎重にならざるをえない。今回延期を発表した企業の帳簿に数字の合わない項目があったため、会計士が監査報告書へのサインを拒んでいるのではないか」と推察する。
低迷する「中国不動産市場」
中国当局によって昨年6月以降から行われた債務圧縮強化の影響で、中国不動産市場は減速している。
中国国家統計局が1月17日に発表したデータによると、21年の中国全土における不動産開発投資は前年比4.4%増の14兆7,602億元(約291兆円)、19年比では11.7%増加しており、2年平均で5.7%微増している。そのうち住宅は前年比6.4%増の11兆1,173億元(約218兆円)、オフィスビルは前年比8.0%減の5,974億元(約11.8兆円)だ。
そのほか、分譲住宅販売面積は前年比1.9%増の17億9,433万平方メートル、19年比では4.6%増となり、2年平均は2.3%増加。そのうち住宅は1.1%増、オフィスビルは1.2%増にとどまった。
中国マーケティング誌のCBNDataによると、不動産会社の21年販売額は碧桂園(カントリー・ガーデン)が5年連続トップを維持しており、年間成約額は5,580億元(約11.0兆円)、成約面積は6,641万平方メートルだ。2位は万科(チャイナ・バンケ)で、成約額は6,277.8億元(約12.4兆円)、成約面積は3,807.8万平方メートル。2位から3位に転落した恒大集団の成約額は4,430.2億元(約8.8兆円)、成約面積は5,426.5万平方メートルで、これは目標としていた7,500億元(約14.8兆円)の60%程度だった。
| 企業名 | 純利益 | 純利益増減率(対前年比) | 成約額(対前年比) |
| 碧桂園 | 5238億円 | -23.49% | -2.2% |
| 万科 | 4398億円 | -45.7% | -10.8% |
| 中国金茂 | 916億円 | 21% | 1.9% |
| 龍湖集団 | 4386億円 | 20% | 7.2% |
| 中国海外 | 7850億円 | -8.5% | 2.4% |
| 華潤置地 | 6333億円 | 8.7% | 10.8% |
※3位の「恒大集団」は決算遅延のため除外となる。
「金融緩和政策」が打ち出されたものの…
シンクタンクの中指研究院によると、22年1〜3月期の中国国内100都市の不動産売上高は前年比47.2%減の162.6億元(約3,200億円)。そのうち売上高1,000億元(約1.9兆円)以上の不動産企業は2社だけで、前年から3社減少している。販売面積も前年よりも47.6%減少し、85.1万平方メートルだった。
| 単月売上高 | 前何同期比 | 累計売上高 | 前年同期比 | |
| 1月 | 1207億円 | -23.1% | 1207億円 | -23.1% |
| 2月 | 834億円 | -35.3% | 2012億円 | -34% |
| 3月 | 1135億円 | -48.7% | 3176億円 | -47.2% |
※円換算する際、レートの関係で単月と累計に誤差あり
低迷する不動産市場下支えのため、今年初めから60以上の都市が不動産業への緩和支援策を相次いで打ち出し、最低頭金比率の引き下げや住宅ローンの拡大、住宅ローン金利の引き下げ、住宅購入向けの補助金支給などといった措置を実施してきた。また、中国当局も昨年末から不動産企業への流動性支援策を続々と打ち出している。その内容は以下の通りだ。
(1)21年12月15日、中国人民銀行(中央銀行)が金融預金準備率の0.5ポイント引き下げを決定。
(2)22年1月20日に、20か月ぶりに新規貸出金利の指標となるLPRローンプライムレートの引き下げを公表。3月までは現状の貸出金利の1年物を3.70%、5年物を4.60%として維持しているが、年内にさらなる金融緩和を行う可能性があると見込まれる。
(3)1月16日に21か月ぶりにMLF金利(市中銀行に1年間の資金を融通する中期貸出制度金利)の引き下げを実施。
これに関して中国当局の人民銀行責任者は、「引き続き穏健な金融政策を実施し、今年・来年2年のマクロ政策を統一的にしっかりリンクさせ、中小企業・グリーン発展・科学技術イノベーションを支援し、質の高い発展とサプライサイド構造改革のために適切なマネー・金融環境を作り上げる」と解説を述べている。
しかし、企業側の土地取得意欲は低下しているのが現状だ。22年1〜3月期の土地取得額は前年比59%減の2,272億元(約4.5兆円)。さらに3月の人民元建て社債と外貨建て債券の発行規模はそれぞれ前年比で-36.55%、-80.7%となり、いずれも大幅な減少を記録した。
中国は、この危機を脱却できるか
中国の住宅市場での人口減少による需要低下は避けられず、これは不動産業への供給過剰によるバブル崩壊とみることもできるかもしれない。
新型コロナウイルス感染を厳格に抑える「ゼロコロナ政策」による景気の低迷や、ウクライナ危機を背景とする資金の流出圧力が強まるなかで、中国は過去20年の高成長期の終焉を認め、現在の危機を脱出することが出来るだろうか。
写真:ロイター/アフロ