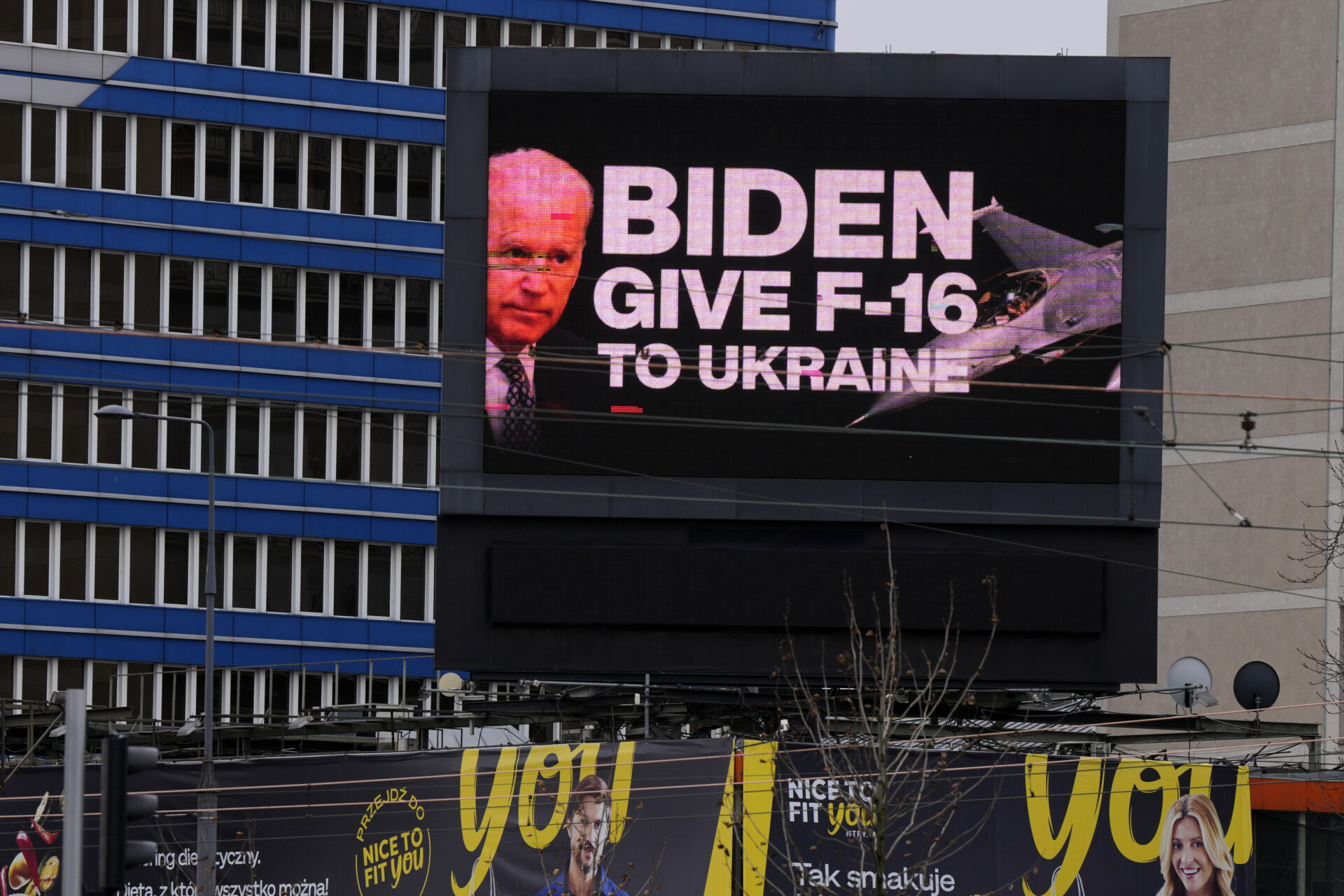中国の強い圧力にさらされながらも、台北市内は活気に満ちている。現地で暮らす筆者の印象では、台湾の日常生活の中で有事が迫っている脅威は感じられない。台湾の離島も普段とほとんど変わらない平穏な日々が続いている。
人々が普段通りの日々を過ごす一方、台湾総統選挙からおよそ1カ月を経た2024年2 月、日常生活の中では少し目に触れにくい金門島の周辺海域において、中国と台湾の間で一つの「事件」が起きていた。金門島は、中国大陸に最も近接する台湾の離島の一つで、冷戦時代の国共内戦の前哨地でもあり、対岸の福建省の廈門(アモイ)からわずか2㎞に位置している。
この金門島付近で起きたトラブルの経緯を追うことで、頼政権発足以降、対台圧力を強める中国の姿勢がいかなるものなのかが浮かび上がってきた。
頼政権発足に圧力をかける中国
2024年5月20日、民進党の頼清徳氏が台湾の新しい総統に就任した。台湾で直接民選総統選挙が開始されて以来、同一政党が三期連続で総統選挙に勝利したのは史上初である。この日、台湾総統府前の広場に集まった台湾市民を前に演説した頼総統は、「中華民国と中華人民共和国は互いに隷属しない」と述べ、台湾がすでに独立した主権国家であることを強調した。中台の正統性を巡る争いを棚上げし、中国側が台湾側との対話のよりどころとしてきた「92年コンセンサス」には触れず、中国と一線を画していく姿勢を鮮明にした。
頼総統の就任演説に対して、中国はすぐさま反論の声明を発表。台湾政策を担う中国国務院台湾事務弁公室は、民進党が台湾の独立分離に固執しているとして非難し、「一つの中国」原則の順守を強く主張した。その上で、「広範な台湾同胞の団結を図り、両岸関係の平和的発展、融合的発展の推進に努力し、祖国統一の大業を揺るぎなく推進する」という立場を示した。
頼の総統就任式から3日後の5月23日、中国は台湾に軍事的な圧力をかけた。中国人民解放軍東部戦区は台湾海峡をはじめとして、台湾北部、南部、東部や、金門島、馬祖島、烏丘嶼、東引島周辺で陸軍、海軍、空軍、ロケット軍を集結。台湾をぐるりと取り囲むようにして、合同軍事演習「聯合利剣2024A」を実施した。軍事面だけではない。5月末には、中台間の実質的な自由貿易協定である「海峡両岸経済協力枠組み協定」(ECFA)に基づく台湾製品(特恵関税率を受けるアーリーハーベストの対象134品目)の関税引き下げ措置を停止すると発表。9月下旬には台湾産の農水産物34品目のゼロ関税優遇措置を撤廃し、台湾に対する経済的圧力を一段と強めている。
よく報じられているこれらの動きの水面下で、金門島周辺海域でのトラブルを巡る中台の駆け引きがなされていた。
平穏な日々の中で高まる緊張
事の発端は、台湾側が領海とする金門島周辺の禁止水域内で起きた事故だった。2月14日、同水域内で操業していた中国籍の漁船が、台湾の海洋委員会海巡署の巡視船の取り締まりのための追跡から逃れる際に転覆。中国人の乗組員4人が海に投げ出され、うち2人が死亡した。この転覆事故を機に、中国は台湾に対する批判を強めた。中国国務院台湾事務弁公室は、「廈門と金門の間に禁止水域や制限水域(接続水域)は存在しない」という声明を発表。これに対して、台湾の大陸委員会は、金門島周辺の禁止・制限水域は、1992年の両岸人民関係条例に基づき設置したものであると反論した。
中国海警局は、この「事件」に対する対抗措置として、同水域で巡視活動を常態化させる方針を表明し、すぐさま実行に移した。それ以降、金門島や馬祖島の沖合で、海警局の船がパトロールのために金門島の周辺の禁止水域や制限水域を航行する動きが頻繁に見られるようになる。2月19日には、金門沖合を航行していた海警局の巡視船6隻のうち1隻が、台湾の観光船に乗り込み、立ち入り調査を実施した。
中国漁船の転覆事故を受け、中台間で15回にわたり協議がなされた。中国側は台湾海峡の中間線を認めず、廈門と金門の間に禁止水域や制限水域はないとの従来の立場を維持し、 「漁船の取り締まりは中国の主権問題だ」と強く主張した。そのため議論は平行線をたどり、3月5日には交渉は決裂。台湾海峡の軍事的な緊張が高まった。
3月7日、台湾の邱国正国防部長(当時)は、立法院外交国防委員会で、中台の軍事的緊張がかつてなく高まっている背景として、中国が台湾海峡の中間線を無視し、防空識別圏への侵入を繰り返していることを挙げた。その上で、国防部や軍は戦争を望んでいないものの、万が一開戦となれば、決して逃げることはないと発言した[1]。
その間、台湾海峡の上空では中国軍機の中間線越えや防空識別圏への侵入、偵察気球の飛来などがあり、海上では海警局の船による台湾の禁止水域への侵入が何度も繰り返された。3月27日には、中国の海上保安機関の下部組織である福建海事局、上海海事局、および東海航海保障センターが、台湾海峡の西側水域で大規模な合同巡視活動を実施した。
中台間の緊張が高まる中、金門島や馬祖島の周辺海域では海難事故が相次いだ。3月14日、金門沖合で中国漁船が沈没し、中台の当局が共同で救助に当たり、6人のうち2人が救助されたが、2人が死亡、2人が行方不明となった。3月17日には金門島周辺で釣りをしていた台湾人2人が遭難。中国福建省泉州で中国海警局の船に救助されたが、そのうちの1人が軍人と判明し、留置の上、取り調べを受けた。7月2日には、海警局が金門島の周辺海域で、中国の領海内を航行していた台湾籍の漁船を拿捕(だほ)する。
日米の「外圧」による緊張緩和
2024年夏ごろになって、金門島周辺で起きた一連のトラブルに関する進展が見られるようになる。7月30日、中台の代表者による協議が金門県で行われ、合意文書に署名がなされた。台湾側は、棺に納められた漁師の遺体と押収した船舶を返還するとともに、中国側の遺族に対して見舞金(約150万人民元)を支払った。
中国側は、「悪意ある衝突事件」という言葉を最後まで取り下げなかったものの、「事件が発生してから5カ月以上が経過し、ようやく双方の善後処理協議が合意に至った」と発表した[2]。一方、台湾の大陸委員会は、両岸双方が解決を望み、互いに誠意を示した結果であるという声明を出した[3]。
その後、3月に中国海警局の船に救助され、取り調べを受けていた台湾の軍人の男性は、職務とは関係なくたまたま遭難したことが判明し、8月上旬に無事に帰還。中国では、本件の取り調べの最中も、台湾から親族を呼び寄せ、面会の機会を作るなど、温情ある対応が取られていたことが報道された[4]。また、7月に海警局に拿捕された台湾籍の漁船については、8月上旬に船長を除く乗組員全員が送還された。
では、なぜ中国側は台湾への歩み寄りの姿勢を見せたのだろうか――。明確な答えはない。ただ、金門島の周辺海域で中台の緊張が高まるのと時を同じくして、台湾を巡って第三国による動きがあったのは事実だ。
その一つが、米国の動きである。米国は、中国漁船の転覆事故によって中台間の緊張が高まっていることに対し、両者の交渉が決裂した後も、双方が対話によって平和的な方法で解決するように呼びかけてきた。また、2024年4月、米議会調査局が発表した台湾の防衛に関する報告書の中で、米国防総省の資料を引用し、2023年12月の時点で米軍人41名が台湾に派遣され、任務に就いていることが公開された[5](ただし、米軍の派遣場所や任務の内容についてはいまだ明らかにされていない)。これまで幾度も米軍が秘密裏に台湾軍の訓練支援を実施していることが報じられてきたが、米国政府がこれを公式的には認めたのは今回が初めてのことであった。
さらに、2024年6月12日には、台湾海巡署の巡視船「新竹艦」が、ハワイ・ホノルル港に寄港し、停泊していることが判明した。「新竹艦」の具体的な任務については公表されなかったものの、折しもハワイ周辺海域では米軍主催の環太平洋合同演習(リムパック)が6月末に始まるタイミングであったことから、海上警備を巡る米台間の深い関係を象徴する出来事として記憶に刻まれることになった。
もう一つが、日本の動きだ。2024年7月、日本の海上保安庁と台湾海巡署は、千葉県房総半島の南方の海上にそれぞれ巡視船を派遣し、合同で捜索や救助などの訓練を実施したことが公表された。日台の海上保安当局による合同訓練は、1972年の断交以来、初の出来事となった。日本政府は、「中国を含む第三国を念頭に置いたものではない」との公式見解を示したが、海上警備の分野における日台の連携が国際社会に強く印象づけられることになった。
以上見てきたように、日米による台湾をバックアップする動きは、中国に対する「外圧」となり、中台の和解を促す一つの要因となったと推測できる。今回の金門島の周辺海域で起きた一連のトラブルの経過をたどる限り、中国は、少なくとも現時点で、対立激化を望んでいないことが分かる。
ただし、8月以降も中国海警局が台湾海峡周辺での巡視活動を常態化させる方針を打ち出し、実行に移している点は見逃せない。今後、中国の姿勢がさらに強硬なものとなり、現状変更の試みに結びつくか否か、引き続き慎重に見極めていかなければならない。
防衛に対する意識を高める台湾市民
先述のように、台湾社会が平穏な雰囲気に包まれているとは言え、一般市民が中国の脅威を全く気に留めていないわけではない。蔡英文政権から頼清徳政権へ移行した後、18歳以上の男性に義務付けている兵役義務の期間が従来の4カ月から、1年へ延長された。毎年実施されてきた台湾の国防費の増額を支持する声も根強い。
台湾の国防安全研究院の世論調査(2024年3月)によれば[6]、2024年1月に徴兵期間が1年間に延長された後の初回入隊が開始されたが、8割以上(83%)の市民が兵役期間の延長に賛成。約4割の市民は国防予算が不足していると考え、約6割が国防予算をGDPの3%まで引き上げることに賛成している。2025年度の台湾の防衛費は、特別予算などを含めて6470億台湾ドル(約2兆9000億円)に上り、過去最高額となった。
言うまでもなく、台湾の安全保障の鍵を握っているのが米国だ。今秋の米大統領選挙の結果にかかわらず、台湾自身が中国の脅威から自らを守ろうという覚悟を示さなければ、米国をはじめ第三国から支援を得られなくなるリスクが付きまとう。上記の調査からも、平穏な日常を享受しながらも、自国がそうした厳しい現状にあることを台湾市民も十分理解している。40代の台湾人の友人が、かつての2年間の厳しい兵役義務の経験を振り返りつつ、自身の小学生の一人息子が将来1年間の兵役に就くことについて、「1年間では足りない。少なくとも2年間は必要だと思う」と語ったことに、はっとさせられた。
不透明さがはらむ有事勃発の危険性
7月に開かれた中国共産党第20期中央委員会第3回全体会議(三中全会)では、経済政策や国内統制の強化が議題に取り上げられ、習近平政権は、経済成長と社会の安定を同時に実現する方針を打ち出した。権力のさらなる集中と一党支配の強化という意図が見え隠れする一方で、停滞する中国経済に回復の兆しは見られない。こうした情勢を背景に、民衆の不満をそらすため、外に脅威を作り出すといった行動に出る可能性は、歴史の教訓からすれば考えにくい。とはいえ、中国は一党独裁国家であって、すべての決定は指導者である習近平の意向に委ねられていることから、楽観できない状況である。
今後、中国は台湾侵攻に備えて着々と軍備増強を進めつつ、軍事・非軍事の両面から台湾に対する圧力を継続すると同時に、「グレーゾーン戦略」を展開し、台湾海峡では平時と有事の境界が曖昧な状態が続くことが予想される(図1)。ただ、台湾有事は、図のイメージに示したような薄いグレーから濃いグレーへと段階的に進むわけではなく、実際にはさまざまな組み合わせによって複合的かつ同時並行で起こってくることが予想される。こうしたグレーな状況の継続は、些細な衝突や行き違いによる台湾有事勃発の危険性をはらむことになる。ひとたび台湾有事が起きれば、海上輸送の混乱や在日米軍基地への攻撃が現実のものとなり、日本もその影響を避けることは困難である。そのような事態を未然に防ぐため、時として、国際社会、特に日米による硬軟織り交ぜた「外圧」が必要となってくる。
【図1】台湾有事のイメージ

2024年9月13日、ドイツ海軍は2隻の艦艇が台湾海峡を22年ぶりに通過したことを発表し、自由で開かれたインド太平洋の重要性を再確認した。同月26日には、日本の海上自衛隊の護衛艦「さざなみ」が、台湾海峡を初めて通過した。それと同じ日、オーストラリアとニュージーランドの艦艇も台湾海峡を通過。さらに、同月28日には、南シナ海で、台湾海峡を通過した海上自衛隊の護衛艦が、米国、フィリピン、オーストラリア、ニュージーランドの海軍とともに共同の訓練を行った。こうした国際的な動きも、日米の取り組みと同様に、台湾の民主主義と安全保障を支え、地域の平和と安定を図るための重要な役割を果たすことつながっていくことになるだろう。
写真:ロイター/アフロ
[1]「『第一擊』要件更改 邱國正:共軍實體越界就反制」『自由時報』2024年3月8日。https://news.ltn.com.tw/news/politics/paper/1634496
[2]「“2·14”撞船事件遇難者家屬與台方就善后事宜達成共識」人民網、2024年8月1日。http://tw.people.com.cn/BIG5/n1/2024/0801/c14657-40290370.html
[3]「在兩岸雙方妥善處理下,『金門0214意外事件』順利落幕」中華民国大陸委員会、2024年7月30日。https://www.mac.gov.tw/News_Content.aspx?n=05B73310C5C3A632&sms=1A40B00E4C745211&s=282613F6EDA86499
[4]「获救金门士兵胡钧翔返乡」新華網、2024年8月7日。http://www.xinhuanet.com/20240807/18d4f1aaee9349de8e84b93cc513da19/c.html
[5]Congressional Research Service. Taiwan Defense Issues for Congress. R48044, April 19, 2024. https://crsreports.congress.gov.
[6]国防安全研究院「台灣國防安全民意調查」最新第一波(2024年3月)調查(筆者による同研究院への公開・使用申請によって資料を入手)。
地経学の視点
台湾市民が日常を過ごす一方、台湾海峡では中台の激しい駆け引きが続く――。現在、台湾に居を置く筆者だからこそ感じることができる現状だ。しかし、その日常の中にも、徴兵期間の延長や年ごとに増える防衛費の増額など、台湾有事という最悪の事態を嫌でも身近に感じる機会も増えている様子もうかがえる。10月14日には、今年2回目となる中国軍による台湾を取り囲むような実動演習も実施された(中国軍が繰り返す台湾近海での実動訓練、4つの特徴から見える意図と侵攻の形参照)。
肝要なのは、中国が暴挙に出ることを国際社会が未然に防ぐことにある。筆者が指摘するように、隣国のわが国や米国が台湾をバックアップしていくことは必須だ。房総沖における日台の巡視船の合同訓練の実施は、台湾有事抑止の動きとして大きな前進だったと言える。今後も、日本がこうした動きに積極的にコミットすることが求められる。
11月には米大統領選を控えているが、共和党候補のドナルド・トランプ前大統領は、半導体開発を巡り、台湾を批判するかのような発言をしており、不確定要素も多い。台湾有事の勃発は、日本の経済活動や日常生活に負のインパクトが大きい。防衛通でも知られる石破茂新首相には、米国のみならず国際社会をも巻き込んだ外交・防衛政策の展開が期待される。(編集部)