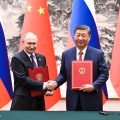11月22日に岸田首相に提出された「国力としての防衛力を総合的に考える有識者会議」の報告書は、日本がこれから取るべき安全保障政策について大きな方針を示している。実業之日本フォーラムでは全5回の予定でその内容を読み込んでいく。第2回である本記事は「防衛産業の育成」についての言及を読み解きながら、その実現に向けて解決しなければならない課題を示したい。
報告書には従来の日本の安全保障政策を大きく転換させるような提言がいくつか含まれており、年末までに策定予定の防衛3文書(国家安全保障戦略、防衛計画の大綱、中期防衛力整備計画)の内容にも大きな影響を与えると思われる。どのような提言がなされたのか。
まず、「防衛産業の育成」についてだ。現在、各企業の一部は防衛産業からの撤退を始めつつある。この現状を踏まえ、防衛産業強化のためには国内環境を整備することに加え、防衛装備移転を進める必要があると指摘された。防衛装備の輸出や譲渡を制限する「防衛装備移転三原則」やその運用指針については、できるだけ制約を取り除いた形で政府主導の防衛装備移転を進めたい考えだ。
これまで、オーストラリアへのそうりゅう級潜水艦、インドへのUS2救難飛行艇、ヨーロッパへのP1哨戒機の輸出などが話題に上っていたが、実際に輸出に至ったのはフィリピンへの防空レーダーだけだ。スウェーデンのストックホルム国際平和研究所(SIPRI)によると、韓国は榴弾砲K9をインド、ポーランド、フィンランドなどに輸出しており、インドネシアには揚陸艦や戦闘機などを輸出している。政府系の韓国輸出入銀行によると、韓国の防衛産業輸出額は昨年70億ドルだったが、今年は100億ドルを超えると見られている。日本と比較すると雲泥の差がある。
日本は2014年に、実質的に武器輸出を禁止していた「武器輸出三原則」を改正し、「防衛装備移転三原則」を制定している。日本の安全保障に資する場合などの一定の条件下で輸出を認めるようにした。とは言え、運用指針においては「救難、輸送、警戒、監視及び掃海」に係る防衛装備に限定するなど、いまだ多くの制約を課している。今回の提言は、これら制約の撤廃や緩和が防衛産業育成強化に必須との考え方によるものであろう。
しかし、民間企業の防衛産業からの撤退は、このような制度の見直しだけでは不十分だ。
武器製造すれば「死の商人」と呼ばれる…!?
その理由の一つが、民間企業が防衛産業に参入する場合に受ける「レピュテーション(評判)・リスク」の存在だ。
どの国においても、戦車、護衛艦、ミサイルなどの武器を製造する民間企業を「死の商人」と称するグループが存在する。日本でも第二次世界大戦の教訓から、昔ほどではないにせよその感覚が残っている。2016年には、奈良県が誘致を進める陸上自衛隊駐屯地を巡って、共産党奈良県会議員などによる団体が「陸上自衛隊は『人殺し』の訓練(を行っている)」と記したチラシを配っている。
また、中国市場との取引がある企業が防衛産業への参入に躊躇(ちゅうちょ)することはよく見られるが、これもレピュテーション・リスクに含まれる。一般に、防衛産業に係る企業の1社あたりの売上比率に防衛が占める割合は4%程度と言われている。わずか4%のために他の事業に悪影響を与えるようなことは避けたいというのが自然な考え方であろう。
日本の科学者は軍事研究しにくい?
また、軍事関連の研究を考える際は、日本学術会議の存在も知っておきたい。日本の科学者の代表機関である日本学術会議は2017年3月24日、「戦争を目的とする科学の研究は絶対にこれを行わない」という過去の声明を継承することを明らかにしている。そのうえで防衛装備庁の安全保障技術研究制度に対して「政府による研究への介入が著しく、問題が多い」と述べ、これが同制度を利用しようとする科学者への圧力となっているのが現状だ。
これを巡って同会議の梶田隆章会長は今年7月、先端・新興科学技術の多様性・両義性の観点から、これを事前に評価・規制することは容易とは言えず、広範な観点から管理することが重要と述べた。この発言は、一部で「軍事研究の容認か」と受け止められたが、同会議はその後も2017年の声明を見直す動きを示してはいない。
科学者に軍事関連の研究を行わないことを勧めるようにも見えるこの姿勢は、企業や大学の技術者に「レピュテーション・リスク」を感じさせる要因となっているかもしれない。
民間企業が、防衛装備移転に消極的なワケ
政権交代や政策変更に伴って移転先での事業が中止されるリスクがあることも、企業を及び腰にしている。よい例がオーストラリアの潜水艦事業だ。前述のとおり、日本は企業が中心となってオーストラリアにそうりゅう級潜水艦の売り込みを行ったが、最終的にはフランスの企業に敗れた。その背景に、装備の優秀さとは別に地元産業育成を含む政治的取引があったことは確実だ。しかしそのような政治的取引も、豪英米の新たな安全保障枠組み「AUKUS(オーカス)」には無力であった。フランス企業の契約は破棄され、それに代わって米国と英国がオーストラリアの原子力潜水艦取得に協力することになった。
フランス企業が売込みに要した費用や事前の投資がどの程度であったかは不明だが、そのすべてが無に帰したことは事実である。もちろん、オーストラリアとフランスの両政府がある程度補償したとは思われるが、防衛装備の移転には同様のリスクが常に付きまとう。このようなリスクを減らすためにも、政府は防衛装備移転に積極的に関与すべきだと言える。
外国と「装備武器の共同開発」を始めよ
第二次世界大戦後に確立された戦後レジームともいうべき、長年にわたって続いてきたレピュテーション・リスクや急な政策変更に伴うリスクを一朝一夕に解決する早道はない。
そこで、まず進めるべきは「装備武器の共同開発」だ。日本は、米国とF2戦闘機や最新鋭の迎撃ミサイル「SM3ブロック2A」を共同開発した実績がある。さらに、英国と空対空ミサイル(AAM)や次世代戦闘機の共同開発に踏み出す予定もある。これを東南アジア諸国を始めとした国々に拡大していくことで、種々のリスクを1社の企業のみで負う危険性を回避できる。
米国や英国などの武器先進国との共同開発においては、日本が得意とする素材や素子の分野が武器サプライチェーン(供給網)の重要な地位を占めることが期待できる。これは日本の存在感や発言力の向上につながるだろう。東南アジア諸国と共同開発は、当該国の技術基盤の拡大につながるとともに、有事における装備のサプライチェーンのレジリエンス(回復力)確保にも貢献する。
こうして防衛装備移転の実績を積み上げていけば、将来的に防衛装備完成品そのものの移転につながっていくだろう。
他国軍への支援、非ODAに限定する必要はない
報告書では、防衛装備移転推進の観点から、同志国の軍に対する政府開発援助ではない非ODAの無償協力による支援を「特定安全保障国際支援事業」として特定することが提案されている。
総合的防衛体制として日本各地の港湾や道路のインフラ整備を防衛力としてカウントするという考え方に立てば、同志国の軍等に対する支援をことさら非ODAに限定する必要はないとも思う。ODAを戦略的に運用し、ODA対象国の軍を含む公共インフラ整備を防衛装備移転と関連付け、移転を促進することも検討すべきではないだろうか。
存在感拡大が安全保障に直結する
先端技術の優劣が軍の優劣に直結し、戦争そのものの帰趨を左右する可能性が拡大しつつある。さらに、技術革新が加速する現在、戦闘様相が一変する新たな技術が急に出現する可能性も否定できない。
岸田政権下で成立した経済安全保障推進法のなかでも、国の支援や官民パートナーシップ、シンクタンク機能の創設が取り上げられている。有識者会議の提言は、防衛3文書のみならず経済安全保障推進法にも反映すべきだ。現在は重要物資や技術の保護に重点が置かれているが、そこから一歩進め、それらの物資や技術をツールとして日本の存在感を拡大していくことも必要だ。
私たちは、国際社会における存在感の拡大こそが日本の安全保障に直結するという認識を共有しなければならない。
写真:ロイター/アフロ