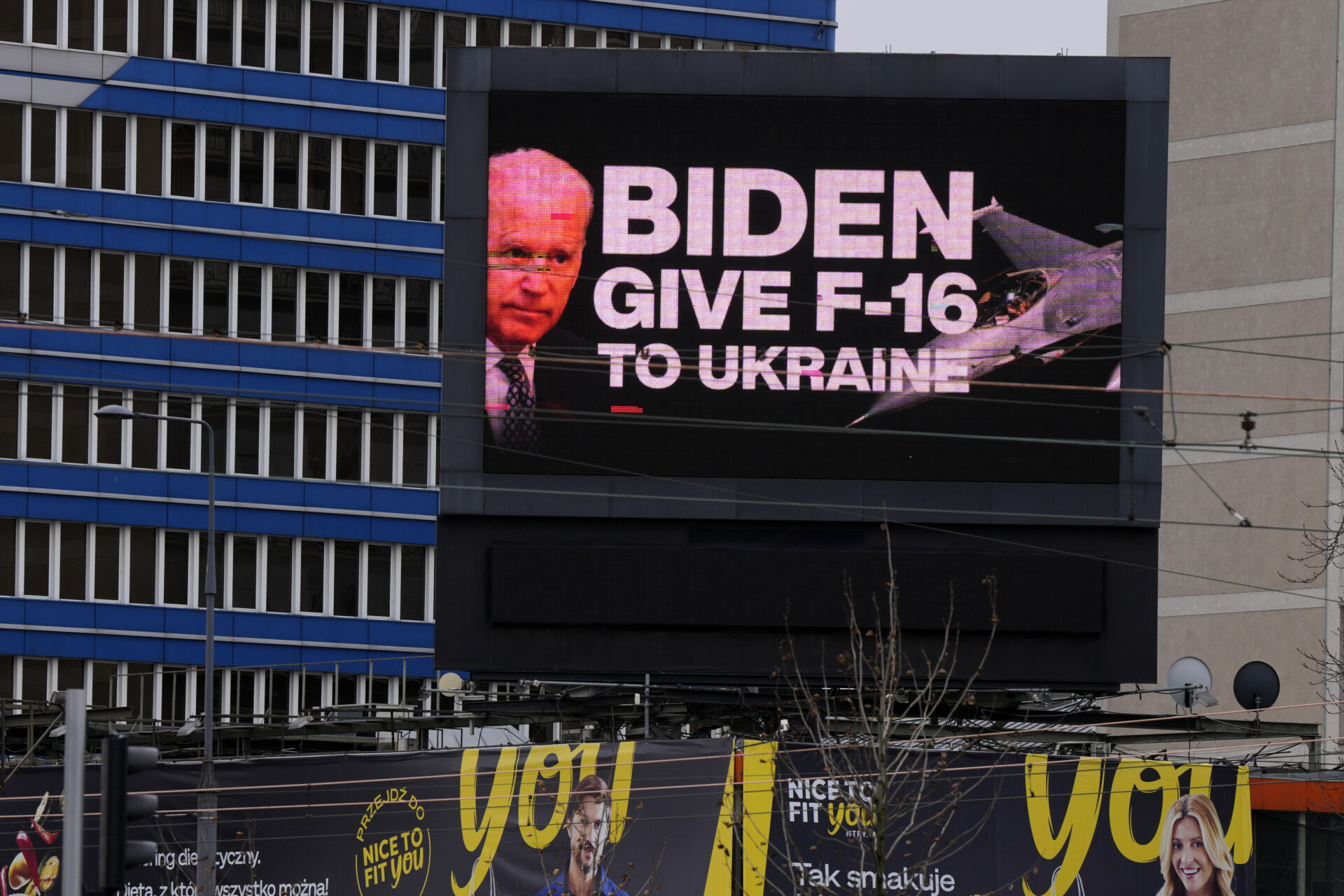ゲスト
野口悠紀雄(一橋大学名誉教授)1940年、東京に生まれる。 1963年、東京大学工学部卒業。 1964年、大蔵省入省。 1972年、エール大学Ph.D.(経済学博士号)を取得。 一橋大学教授、東京大学教授(先端経済工学研究センター長)、スタンフォード大学客員教授、早稲田大学大学院ファイナンス研究科教授などを経て、一橋大学名誉教授。専門は日本経済論。『中国が世界を攪乱する』(東洋経済新報社 )、『書くことについて』(角川新書)、『リープフロッグ』逆転勝ちの経済学(文春新書)など著書多数。
聞き手
白井一成(株式会社実業之日本社社主、社会福祉法人善光会創設者、事業家・投資家)
白井:アベノミクスで構造改革への期待が高まりましたが、日本は古い構造からなかなか変 化できていないようです。野口先生の『リープフロッグ 逆転勝ちの経済学』でも、アベノ ミクスの期間に日本の凋落は加速しており、IMD 世界競争力ランキングでの日本のデジタ ル技術は63ヵ国中62位であることを指摘されています。
野口:アベノミクスで「三本目の矢」、構造改革が進まなかったと言いますが、アジェンダ が具体的に決まっていなかったのであれば、成功しなかったのは当然でしょう。
高度成長期の日本経済は、明らかに輸出立国型でした。日本に必要なのは、産業構造を従来型の製造業から高度サービス産業を中心とするものに変えていくことですが、それは達成されていません。特にアメリカやイギリスと比べると、日本の産業構造で製造業の比率は顕著に高く、ドイツと似た構造です。それが問題です。
1980 年代から新興国が工業化し、中国を初めとする新興国が製造業を担当するようになりました。豊富な労働力によって、非常に安い製品を作れるようになってきた。つまり、製造業は先進国型の産業ではなくなってきたのです。
一方、アメリカやイギリスなどの産業構造は、サービス産業に大きく転換しました。特に、高度サービス産業と言ってよいと思いますが、付加価値の高いサービス産業に移行し たことで、所得が高くなっています。このような転換をした最も典型的な国はアイルランド という小さな国です。アイルランドは工業化を実現できませんでしたが、情報産業に適合し、 今や世界で最も豊かな国の一つです。
ドイツや日本がそういう転換ができなかった理由はいろいろありますが、日本の高度 成長を支えたのが製造業であり、その製造業が経済政策に強い影響を与えているということが影響しているのでしょう。製造業が居座っていることが原因です。そもそも産業は政府が旗を振って育成できるものではなく、基本的には民間が努力するしかありません。
白井:GDPに占める製造業の割合を見ますと、日本、アメリカ、中国、ドイツの4ヵ国の中では中国が40%と、製造業への依存度が最も高くなっています。次いで高いのがドイツで24%、日本が22%です。アメリカは11%と製造業が占める割合は低く、不動産、サービス業などその他部分が占める割合が高くなっています。
野口:もう一つの重要な点は、製造業において、世界的な水平分業化という大きな変化が生じたことです。従来の製造業は、ひとつの企業の中で部品から最終製品まで全部作るという、垂直統合型で生産していました。鉄鋼や自動車がその典型です。テレビの生産の「亀山モデル」も、ひとつの大きな工場の中で部品から最終製品まで全部作るという方式です。
しかし、水平分業では、新興国の工業化がうまく活用されました。最大の成功例はアップルでしょう。それまでアメリカの国内でコンピュータを生産していたアップルは、2004年頃のiPodから、世界中で作られた部品を中国で組み立てるという水平分業の仕組みに転換しました。工場がない製造業、ファブレスと言いますが、それが製造業の中心的な形になってきました。
日本でもそのような転換が必要でしたが、成功しませんでした。あるいは、そうした転換 が必要とも言われなかった。水平分業に転換できない理由は幾つかありますが、ひとつには、 国内で失業が発生するという問題です。本来、そういう失業が他の産業、特にサービス産業 に移っていくことが必要なのですが、そうした転換ができませんでした。もう一つは、製造業が従来の形に執着し続けたことです。
このような状況を変えるのは非常に難しいと思います。いまの状況を見て、そういう変化が生じるようなきっかけを見出すことができません。必要なのは国民が豊かになることで、そのためには日本の生産性を上げる必要があるのです。高度成長期の日本が、製造業、特に輸出産業を中心にして発展してきたことは間違いありません。生産性を上げるためには、従来とは違う産業構造が必要になるのです。
生産性を上げることと成長は必ずしも同義ではありません。日本の場合には、人口が減少 していくでしょうから、1人当たりの生産性が上がっても、経済全体の成長率は低くなる可 能性があるのです。「豊かになる」というのは、1人当たりのGDPのことです。人口が減少するので、GDPの成長率が低くなるのは不可避でしょう。
労働力を増やす方策は、外国人が入ってくることだけではありません。最近の重要な変化は、在宅勤務が可能になったことです。原理的には、オンラインで移民が可能になりました。インドにいる人はインドにいたままで日本の企業で働くことが可能です。このことはほとんど議論されていませんが、非常に重要です。世界的なスケールでの在宅勤務を進めるべきであり、それは日本の生産性向上に寄与するというのが私の意見です。日本の人口や労働力の増加にはつながらなくても、日本を豊かにする可能性としては大変大きいと思っています。
白井:今後の日本は、アメリカやイギリスのような生き方もあるでしょう。日本は、過去に蓄積したさまざまなハードやソフトの国富を保持しています。日本にはどの道に一番可能性があり、どの道を行くべきとお考えでしょうか。
野口:製造業自体が世界的に垂直統合から水平分業に変わっていくことは不可避です。そう であれば、各々の部分でどうするかです。国際的、世界的な水平分業の中で、ある部分につ いて、ほかの国や企業が真似できないことをやるのは、非常に重要なことだと思います。例えば iPhoneの生産でも、部品はいろいろな所で作られています。ごく一部の部品、ニッチであってもいいから、世界で最もすぐれた製品を作り出すというのはひとつの解になるのではないでしょうか。
白井:日本の最大の輸出産業は自動車産業ですが、折しも日本にとって競争力の象徴である 自動車産業は歴史的な転換点を迎えています。自動車は高い安全性も求められるため、PC や半導体のように日本企業が築いてきた競争力が一夜で失われる可能性は低いでしょう。 ただ、当面はハイブリッド技術で凌ぐことができたとしても、その先のEV化は必至でしょうし、研究開発コスト負担は重石となります。また、車は所有からモビリティサービス利用に移り始めています。ITの進展、スマートフォンの普及により、資産の貸し手と借り手のマッチングが容易になりましたが、シェアエコノミー化は自動車の販売台数に悪影響を与えそうです。サプライチェーンの問題も注目されています。
野口:自動車がなくなるのは考えにくいとしても、現在のガソリン車から、EVや自動運転 車に移行するというように、自動車産業の形が変わっていくことは考えられます。そうした変化に日本が対応できるかは大いに疑問です。自動車のEV化は、自動車の生産が従来のような垂直統合から水平分業に移行していくことを意味します。つまり、自動車をひとつの工場の中で部品から組み立てまで行うのではなく、いろいろな部品を世界各国で作り、それを組み立てるという形になるのです。そうした場合には、モーターや電池などの部品の重要性が高まるでしょう。
(敬称略)