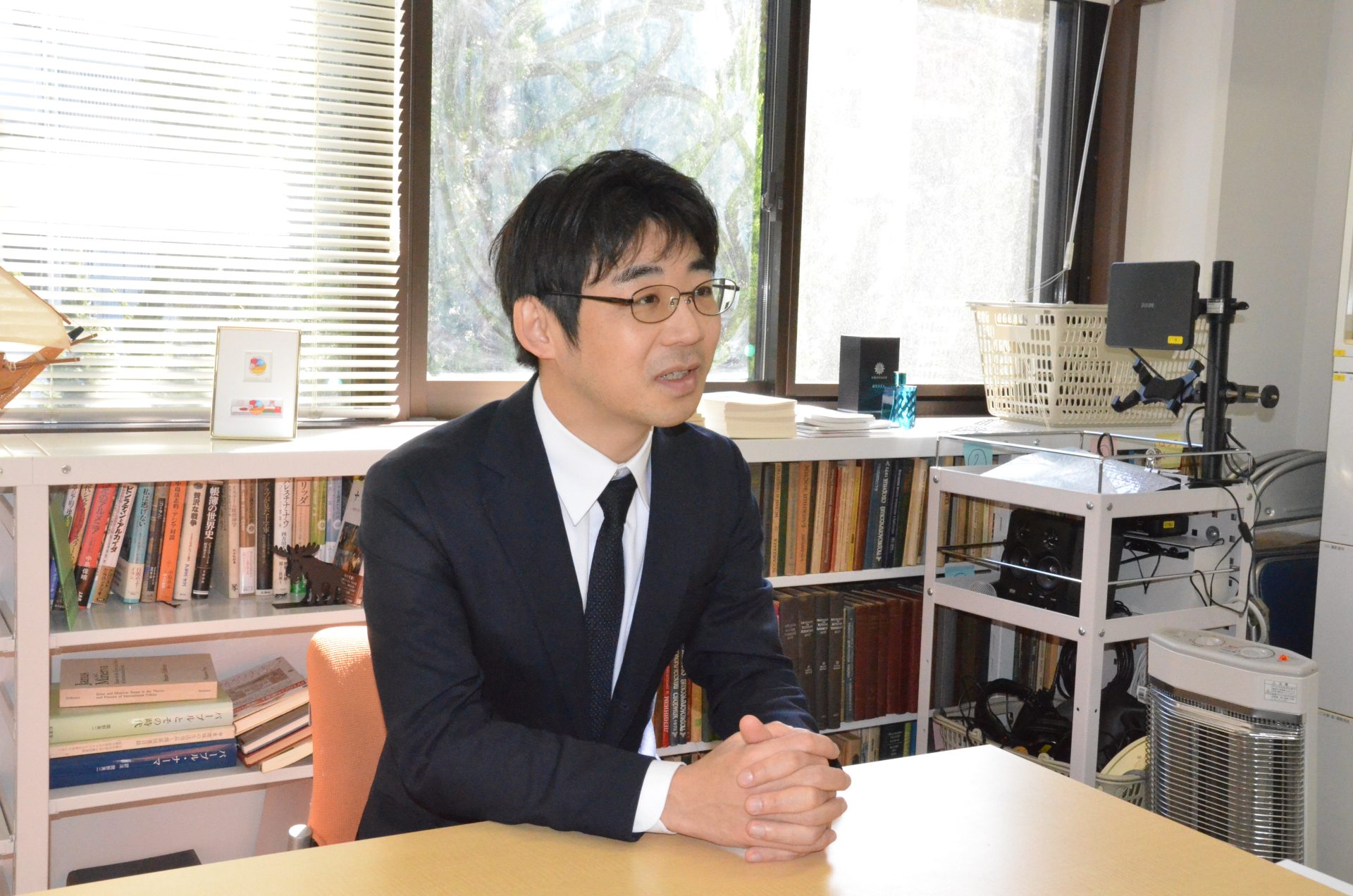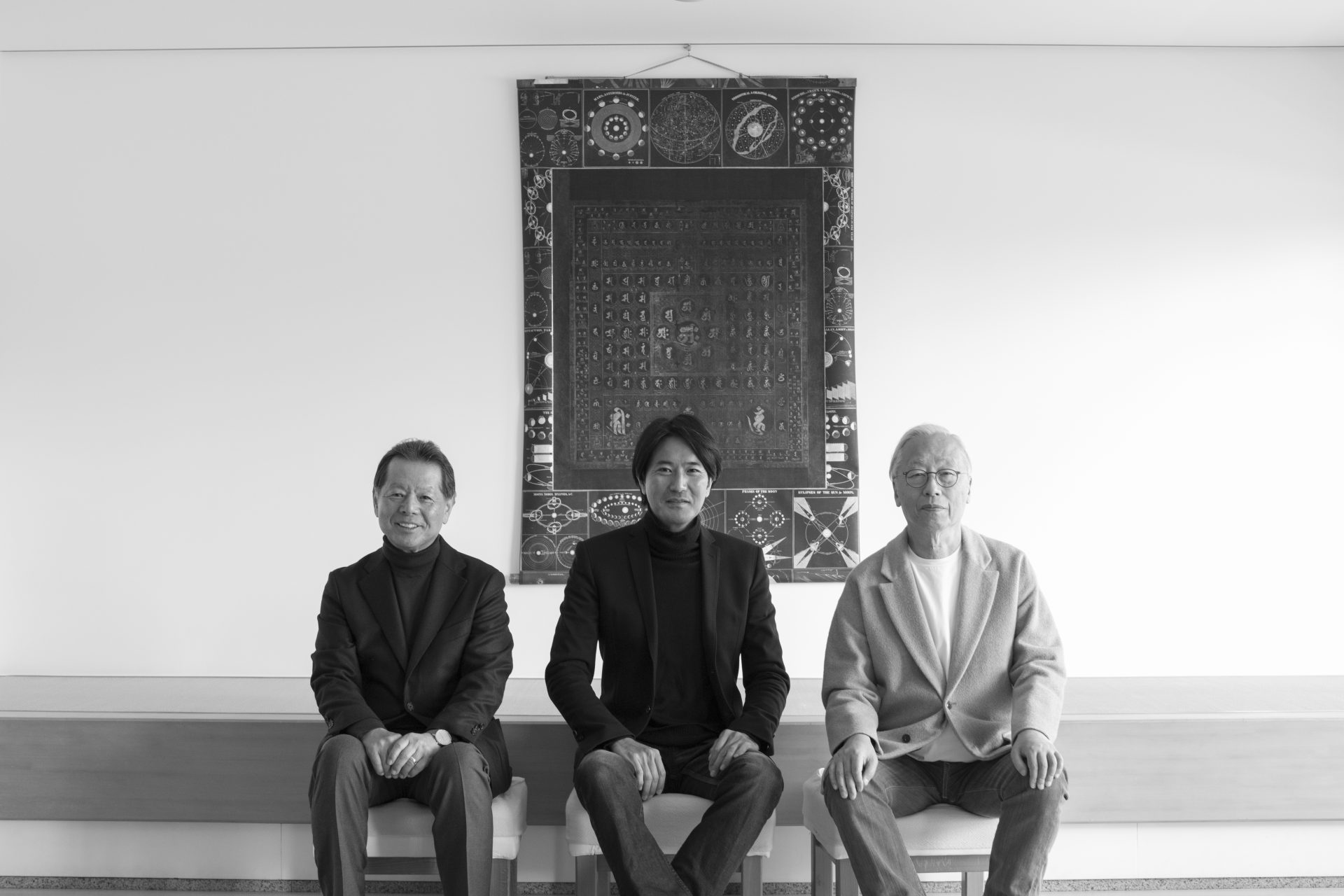技術の発達が戦闘様相を一変させる役割を果たすことがよく知られている。第2次世界大戦における大日本帝国海軍の失敗の一つに、第1次世界大戦中のユトランド沖海戦の教訓から「大艦巨砲主義」一辺倒に陥り、新たな兵器である航空機の役割を軽視したことが挙げられている。「将軍達は、いつも最後に戦った戦争を基準に準備している(Generals are always preparing for the last war.)」という格言がある。昨今の科学技術の発達を見ると、軍事常識を覆す可能性のある先端技術が目に付く。そして、それは先進国に限らない。最近話題となっている極超音速ミサイルを例に考えてみたい。
2021年9月29日付北朝鮮労働新聞は、新たに開発した極超音速ミサイル「火星-8」の試験を行ったと伝えている。飛行操縦性、安全性等全ての技術的指標が設計上の要求を満足したとしているが、細部については明らかにしていない。公開されたミサイルの写真を見る限り、弾道ミサイルの弾頭部に飛翔体を装着した「HGV(Hypersonic Glide Vehicle:極超音速滑空ミサイル)」と推定できる。
今年1月に実施された朝鮮労働党第8回大会において金正恩総書記は、新たな軍事技術を開発又は研究中として5項目をあげた。「多弾頭個別誘導技術」、「極超音速滑空飛行」、「中型潜水艦武装近代化」、「原子力潜水艦」及び「各種電子兵器・無人兵器・軍事偵察衛星」である。今回明らかにされた「火星-8」とされるミサイルは、このうち「極超音速滑空飛行」に該当するものである。北朝鮮が、経済制裁、自然災害及び新型コロナ対策という三重苦の中、新たな軍事技術開発を進めていることは驚きである。
HGVは、弾道ミサイル等で打ち上げられ、成層圏で分離したのち、高度30㎞付近をマッハ5以上の速度で滑空飛行する。韓国国防部は、9月29日のミサイル発射について、速力マッハ3、最大高度30㎞、飛行距離200㎞以上との分析結果を公表している。これが事実であれば、今回の試験は、速度及び高度ともに極超音速ミサイルの定義に達しておらず、初期段階の試験又は失敗であった可能性がある。一方、極超音速ミサイルは米ロ中が互いに相手を圧倒する兵器として開発を進めているものであり、戦略環境を一変させる可能性が指摘されている。
アメリカの極超音速ミサイル開発の発端は、冷戦直後までさかのぼる。平和の配当を求める世論に応じ、世界各地に分散した米軍基地の整理統合が迫られる一方、世界のいかなる場所における、予期しない紛争にも迅速に対応できる体制の整備が求められた。これに対する回答が、「地球上のいかなる場所であっても、1時間以内に攻撃し得る長距離通常兵器を開発すること」であった。これは「CPGS(Conventional Prompt Global Strike)構想」と呼称された。
国防高等研究計画局(DARPA)及び陸海空軍はそれぞれ開発を進め、2010年には米空軍とDARPAが共同開発したHTV-2(Hypersonic Test Vehicle)がマッハ20で9分間の試験に成功した。米陸軍はAHW(Advanced Hypersonic Weapon)を、海軍はCTM(Conventional Trident Modification)を開発、飛行試験を実施したが、成功と失敗を繰り返した。
CPGSは弾道ミサイルの弾頭部に装着して発射されることから、核攻撃と見分けがつかず、核戦争を誘発する危険性があるとの批判があった。更には、度重なる実験失敗もあり、米議会が予算を削減したため、開発は中ロに大きく後れを取ることとなった。現在進められている計画は、SLBM頭部にHGVを装備する方式であり、今年及び来年度に開発予算が計上されている。
アメリカが開発しているもう一つの極超音速ミサイルは、「HCM(Hypersonic Cruising Missile)」である。航空機から発射され、スクラムジェットエンジンを使用しマッハ5以上で飛翔する。2021年9月27日DARPAと米空軍は共同開発中の極超音速ミサイルHAWC(Hypersonic Air-breathing Weapon Concept)がマッハ5を記録したと発表している。
ロシアはHGV、HCM双方の実用化を進めている。HGVのAvangardは2018年12月に飛行試験に成功、マッハ20の速度で、約3,500NM(約6,500Km)を飛行したと伝えられている。さらに、ロシア国防省はHCM、Zirconがフリゲート及び潜航中の潜水艦から発射された映像を公表している。射距離は約1,000Km、最高速度はマッハ9と伝えられている。Avangard、Zircon双方とも核弾頭の装備が可能と見積もられており、ロシアの対地攻撃能力は、飛躍的に向上したと言えるであろう。
中国は2019年10月の軍事パレードにおいて、DF-17とペイントされた新型ミサイルを公表した。形状からHGVと推定され、射程は約2,500㎞、核弾頭装備可能と分析されている。米インド太平洋軍の議会報告によれば、中国は2025年までに極超音速ミサイルを200基以上保有すると見積もられている。さらに、スクラムジェットエンジンの開発も行っているとも伝えられており、米ロに引き続き、中国もHGV及びHCM双方の装備を進めていると思われる。
わが国も、防衛装備庁と宇宙航空研究開発機構(JAXA)が「極超音速飛翔体」の研究開発を共同で行っている。「デュアルモード・スクラムジェットエンジン(DMSJ)」と称されるシステムは、現在地上試験及び風洞実験の段階であり、実用化には更なる時間を要するものと見られる。
現在各国が開発中の極超音速ミサイルの特徴は次の3点に集約できる。「高速かつ低軌道を飛翔するため、継続探知が難しく、迎撃が困難である」、「軌道を途中で変化させるため、弾着点を推定することが困難である」そして「弾頭が通常弾頭か核弾頭かを判断することが困難である」である。この特徴は、核抑止戦略に大きな影響を与える。相手が極超音速ミサイルを発射したことを探知した場合、あまりに高速であるがゆえに、相手の意図や発射されたミサイルを分析する時間が限られ、最悪の事態、核弾頭ミサイルを撃たれたと判断せざるを得ない危険性が増す。これは、「Launch on Warning(LOW)」と呼称される戦略概念であり、相手の発射を確認したならば、弾着を待たずに反撃(核攻撃)を行う。米議会が、CPSGに懸念を示したのは正にこの点にあった。
しかしながら、すでに中ロ両国でHGV及びHCMの実用化が目前となってきた現在、極超音速ミサイルに関し、何らかの国際的合意が必要である。HGV及びHCMに核弾頭は装備しない、あるいは装備する場合は通報するといった国際的合意がないと、誤解に基づく核戦争の懸念は低減されない。今年1月に5年間の延長に合意した「米ロ新戦略兵器制限条約」は、核弾頭数及びその運搬手段としての大陸間弾道ミサイル、潜水艦発射弾道ミサイル及び戦略爆撃等の数を定めている。この条約にHGV及びHCMが含まれるかどうかは明らかではない。更に、この条約はあくまでも米ロ二国間のものであり、中国は含まれていない。アメリカは中国にも参加を呼びかけているが、中国は米ロとの弾頭数の差(米国:6,185発、ロシア:6,500発、中国:290発/ストックホルム平和国際研究所2020年1月発表)を理由に参加に消極的である。現在の条約で規定されている1,500発という弾頭数を更に削減し、極超音速ミサイル技術の流出を防ぐという事を梃に、中国にも参加を慫慂していくべきであろう。
今回は、極超音速技術が戦略環境に与える影響について分析した。しかしながら、戦闘様相だけではなく戦略環境を大きく変える可能性を持つ先端技術は、極超音速技術だけではない。AI、サイバー、ロボティクス、量子コンピューター等の技術も同様の可能性を秘めている。
8月末に防衛省が公表した「令和4年度概算要求の考え方」に初めて「ゲーム・チェンジャーとなり得る技術等の研究開発や防衛産業基盤を強化する」ことがうたわれている。最先端技術は軍民デュアル・ユースである場合が多い。防衛省は2015年以降「安全保障技術研究推進制度」を設け、大学等における革新的・萌芽的技術を支援する制度を設けている。しかしながら、日本学術会議は、大学が軍事技術開発に関与することを忌諱する声明を出し、この動きをけん制している。先端技術はごく一部の研究者の占有物ではなく、国家の安全保障、引いては、それこそが最終的に学問の自由につながるという理解が必要である。
サンタフェ総研上席研究員 末次 富美雄
防衛大学校卒業後、海上自衛官として勤務。護衛艦乗り組み、護衛艦艦長、シンガポール防衛駐在官、護衛隊司令を歴任、海上自衛隊主要情報部隊勤務を経て、2011年、海上自衛隊情報業務群(現艦隊情報群)司令で退官。退官後情報システムのソフトウェア開発を業務とする会社において技術アドバイザーとして勤務。2021年から現職。
写真:AP/アフロ